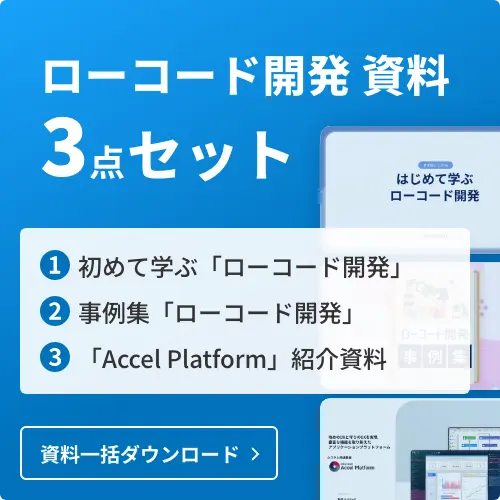ローコード開発コラム
ローコード開発が注目される理由
ローコード開発そのものは、2011年頃から存在していました。
「ローコード開発(low-code
development)」という言葉を初めて使ったのは、
調査とアドバイザリーを手がける米フォレスター・リサーチ社で、2014年のことでした。
以前から存在しているローコード開発ですが、近年、さまざまな理由から、注目を集めるようになりました。
このページでは、ローコード開発が注目される理由をご紹介いたします。
ビジネス環境の変化に合わせ、システムの素早い開発・変更が求められる
ITが業務に導入され始めた当初は、それまでの社内業務に対する「業務効率化」「コスト削減」などの目的が中心での利用でしたが、徐々により戦略的な使われ方へとシフトしてきました。
特に近年は、デジタルトランスフォーメーション(DX)の推進が叫ばれていることもあり、組織におけるIT戦略の位置づけは、より経営の上流へと引き上げられています。IT活用は、商品・サービスそのものへの組み込みや、顧客との関係構築など、よりビジネスに直結するような使われ方へと変化しつつあります。
また、ビジネスを取り巻く環境の変化もスピードアップしています。
加速するビジネス環境の変化についていくためには、業務に利用するシステムを変化に合わせて素早く変更する必要があります。
ローコード開発は、非エンジニアである現場の担当者の手で、短期間で、業務にフィットしたシステムの開発や変更が柔軟に行えるため、期待が集まるようになりました。
IT人材が不足しており、非エンジニアが開発を担う必要がある
現場の担当者の手でシステムやアプリケーションの開発・変更が行えることには、もう一つのメリットがあります。それは、IT人材不足を補えることです。経済産業省がDXの推進を表明した「DX(デジタルトランスフォーメーション)レポート~ITシステム「2025年の崖」の克服とDXの本格的な展開~」 の中で、2018年時点ですでに約17万人ものIT人材が不足しているところから、2025年には約43万人まで拡大するとの推測がなされています。
プログラミングの専門知識を持たない非技術者であっても、簡単にシステムやアプリケーションの開発・変更が行えるローコード開発を活用することで、希少なIT人材の手を煩わせずに済み、IT人材は、より高度な業務に専念できるというわけです。
ベンダー任せによるブラックボックス化を防ぐ必要がある
ローコード開発プラットフォームやノーコード開発プラットフォームを利用せずにシステムやアプリケーションの開発・変更を行う際、自社のIT人材を活用することもできますが、多くの場合は、開発ベンダーに外注することになります。
開発ベンダーに開発や変更を任せ切りにしてしまうと、社内にシステムやアプリケーションの内部を知る人材が育ちにくくなり、その結果、ブラックボックス化してしまいます。
一方、ローコード開発プラットフォームを利用して、社内の現場担当者や情報システム部門などが中心となって開発を行ったり改修を行ったりすることで、開発や変更の経緯を知る人が社内に増え、ブラックボックス化を防ぐことができます。
システム開発における期間とコストを短縮する必要がある
情報システム部門は従来、組織内のITシステムの導入に関する企画・推進や運用を担当する部門でした。しかし、近年は、企業がより戦略的なIT活用を重視するようになり、さまざまな部門においてデータドリブンが進み、DXのプロジェクトなどでも情報システム部門が中心的な役割を果たすようになりました。
また、高度化・巧妙化するサイバー攻撃から組織のITや情報を守る、情報セキュリティ対策のための業務負担も増大しています。
組織によっては、情報セキュリティ対策専門の部門を設けているところもありますが、中小企業など規模の大きくない組織では、情報システム部門が担当していることが多いです。
このような背景から、情報システム部門の業務は拡大し、負荷が大きくなっています。
しかし、これに見合う人員の増強や予算の拡大が行えている組織は、そう多くはありません。
このため、社内で利用するシステムの調達にかけるべき費用も時間も、以前と比べて縮小する必要があります。
そこで、開発期間を短縮し、金銭コストも抑えられるローコード開発プラットフォームが注目されているのです。
今後の成長が期待されるローコード開発市場
上でご紹介したように、ローコード開発は世間から注目を浴びているシステム開発方法です。 日本だけでなく世界的にも期待を集めており、世界的に大きな影響力を持つIT企業群「GAFAM(ガーファム)」も、ローコード開発の企業やプラットフォームを買収したり開発したりしています。
さらに、今後の市場拡大にも期待が持てます。米ガートナー社を始めとする国内外の調査会社などが、ローコード/ノーコードの市場や導入状況について、拡大を予測しているのです。
ローコード開発市場は、今後も成長が見込めるでしょう。