働き方改革推進の問題点と解決策を徹底解説

2019(平成31)年4月に働き方改革関連法が施行されてから、3年が経過しました。現在、多くの企業が、残業の削減や長時間労働の是正、有給休暇取得の奨励などに取り組んでいます。
ただ、取り組みがうまく効果を上げているところばかりではないでしょう。
本コラムでは、働き方改革を推進するに当たり突き当たる問題点と、その解決策をご紹介いたします。
【関連記事】
働き方改革による残業時間 ~残業時間を削減する方法~
働き方改革の課題の解決方法についてわかりやすく解説
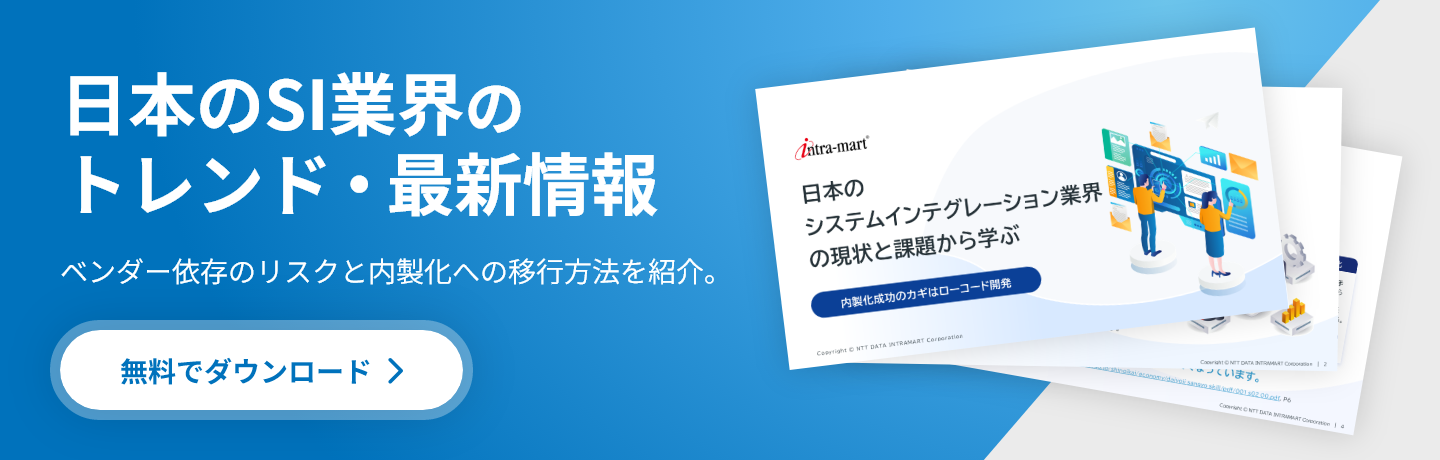
1. 働き方改革が求められる背景
政府が働き方改革を打ち出したのは、少子高齢化と人口減少によって、将来的に労働人口が大幅に減少してしまうことを危惧したためです。
厚生労働省が発表した2020年の「人口動態統計」によれば、日本の合計特殊出生率は1.34で、5年連続の低下となっています。2022年時点で、すでに日本の人口は減少傾向にあり、少子高齢化社会となっています。
少子高齢化と人口減少に伴う労働人口の減少と、その結果、労働生産性が低下することを食い止めるため、時短勤務やテレワークなど従来の働き方にこだわらず、柔軟な働き方を実現することで、出産・育児・介護・疾病などで離職した労働者を労働市場に呼び戻そうというのが働き方改革です。
そのために、長時間労働を是正したり、有給休暇の取得率を向上したり、正規雇用者と非正規雇用者との格差を是正したりといった施策が講じられることになるのです。
2. 働き方改革の問題点とは
では、本題の働き方改革を推進する上で突き当たる問題点を具体的にみていきましょう。
さまざまな問題点を、企業側にとっての問題点と従業員側にとっての問題点に分けて解説します。
企業側にとっての問題点
まずは、企業側にとっての問題点です。
人件費などのコストの増加や、従業員の勤怠管理などがしづらくなるなどの問題が考えられます。
人件費などのコストが増加する
残業を削減して適正化することで、残業代の支払いは抑制できる可能性が高いでしょう。しかし、正規雇用者と同等の業務を行っていた非正規雇用者に対して報酬の差額分を支払うことになったり、生産性を向上させるために新たに導入した制度の実現やITツールの利用料などのためにコストが発生したりします。
その結果、全体的なコストが増加する可能性があります。
従業員の管理がしづらくなる
柔軟な働き方を実現するために、フレックスタイム制やテレワークなどを導入することもあるでしょう。その際、それまでのオフィスへの出勤時と同じ勤怠管理方法や人事評価方法では、従業員を管理ができなくなる可能性があります。
たとえば、勤怠管理をタイムカードで打刻させていた企業なら、オンラインで打刻できるクラウド型の勤怠管理サービスなどを導入する必要がありますし、上司が部下の勤務態度を見て評価を下していた企業では、個々の成果を可視化できるような業務管理体制に切り替える必要が出てきます。
規約などを変更しなければならない
上記とも関連しますが、新たな制度の導入に伴い、それまで運用してきた社内規定などのルールを変更する必要が生じます。変更にあたって、詳細を検討したり、実際に変更してルールを周知したりするためには、それなりの工数がかかります。
その結果、これを担当する従業員の業務が停滞したり、残業代が発生したりと、企業側にも負担が発生します。
従業員側にとっての問題点
次に、企業側にとっての問題点です。
それまで残業代に収入を頼っていた従業員が、収入が減って困ってしまったり、就業時間に対して業務量が過多になってしまったりといった問題が挙げられます。
残業代の分、収入が減ってしまう
なかには、基本給が安く、その分を残業代で補っているという従業員もいるでしょう。そうした人は、働き方改革の推進で残業が抑制されると、生活が苦しくなってしまいます。
その結果、離職につなげる可能性もあり、その点では企業側にとっての問題点ともなり得ます。
就業時間に対して業務量が過多になる恐れがある
長時間労働の是正のために労働基準法などが改正されたのが働き方改革関連法案とよばれるものですが、労働基準法に定められた労働時間規制の対象から除外される労働者がいます。それが、高度な専門知識を有し一定水準以上の年収を得る労働者で、これを定めた制度が「高度プロフェッショナル制度」です。
高度プロフェッショナル制度が適用されると、労働基準法に定められた労働時間や休憩、休日、深夜の割増賃金が適用されなくなります。つまり、残業や休日出勤などの概念がなくなるということです。
この制度が乱用されてしまえば、就業時間に対して業務量が過多な従業員が増える恐れがあります。それでなくとも、残業時間だけカットされて業務量は変わっていないと不満を持つ社員は少なくないでしょう。企業側が、業務を効率化するために業務プロセスを見直したり、ITツールの導入などの対処を行ったりするべきといえます。
3. 働き方改革の問題点を解決する方法
では、こうした問題点を解決するには、どうしたら良いのでしょうか?
前章で触れた内容とも重複しますが、大きく次の4つの方法が挙げられます。
働き方改革に対する目的意識を持つ
働き方改革関連法案の施行に合わせて義務感で取り組みを進めてしまうと、上記のような問題点が生じたり、問題点をネガティブに捉えたりしがちです。
そうではなく、自社が業務の上で抱えている課題を解消するために働き方改革に目的意識を持って前向きに取り組む姿勢が必要でしょう。
まずは、自社の業務における課題を洗い出し、働き方改革に取り組むメリットを認識し、働き方改革に対する目的意識を持つことからスタートしましょう。
業務プロセスを可視化して見直す
業務を改善する際には、まず既存の業務を可視化する必要があります。可視化することで、業務におけるムリ・ムダ・ムラを見つけることができるからです。
それぞれの例と改善方法には、次のようなものがあります。
ムリの例と改善方法
業務改善におけるムリとは、能力以上の負荷がかかっている状態です。たとえば、「一人の従業員が抱える業務量が多すぎる」「人員の配置が適切ではない」といったことが挙げられます。想定以上に業務に時間がかかっているケースなどでは、ムリが発生している可能性があります。
ムリを改善するには、その業務に当たる人員を増やしたり、自動化のためのツール(RPAなど)を導入したり、業務に当てる時間を増やすといった対応があります。
RPAについて詳しくは、下記の記事もご覧ください。
【関連記事】
RPAツールとは?メリットや活用事例、無料ツールを一挙に紹介します
ムダの例と改善方法
業務改善におけるムダとは、上記の「ムリ」の逆で、能力に対して負荷が小さすぎる状態です。たとえば、「二重作業が発生している」「作業待ちの時間がある従業員がいる」といったことがムダの例です。
これを改善するには、たとえば、二重で発生している作業を片方やめたり、人員を削減したりといった対応があります。
ムラの例と改善方法
業務改善におけるムラとは、上記の「ムリ」と「ムラ」が両方存在し、それがランダムに表れている状態です。たとえば、「新人とベテランで同じ業務でもかかる時間や仕事の質に差が出ている」「繁忙期には人員が不足し、閑散期には人員が余剰する」といったことがムラの例です。
これを改善するには、たとえば、人員配置を適正化する、業務を標準化できるようなBPMツールなどを導入・活用するといった対応があります。
BPMについて詳しくは、下記の記事もご覧ください。
【関連記事】
BPMツールとは?業務改善に効果を発揮するBPMツールを比較
業務を可視化することは、上記のようなムリ・ムダ・ムラを発見できるだけでなく、RPAのようなITツールを導入する際にも役立ちます。
業務を効率化してくれるITツールを導入する
業務プロセスや人員配置などを変えるだけでは十分な改善が図れないという場合は、業務を効率化してくれるITツールを導入・活用すると良いでしょう。
ポイントは、情報共有をスムーズにしたり、作業を自動化できるツールを選ぶことです。
また、既に社内で利用しているシステムとの連携が取れるものがおすすめです。
業務をアウトソースする
自社内で業務を完結させることにこだわらず、業務を外注するというのも良い方法です。その業務に特化したアウトソーシング先を選べば、業務の質も向上できる効果が期待できます
業務をアウトソースする場合は、自社のデータを外部へ渡すことになるため、ISOなどの情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)の認証を取得しているところを選び、NDA(秘密保持契約)を締結しましょう。
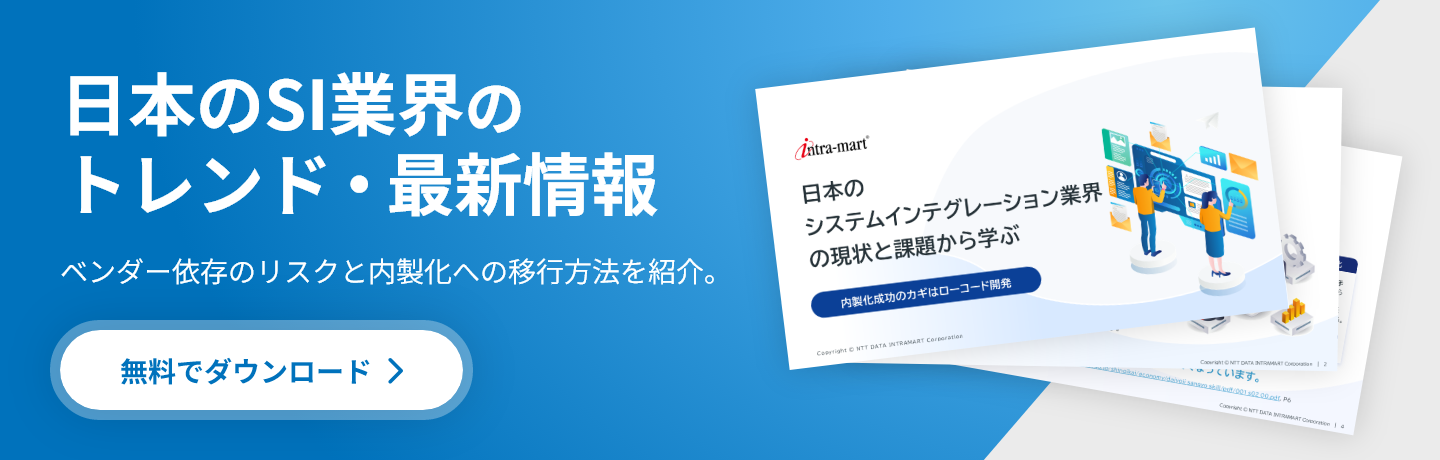
4. まとめ
働き方改革の問題点と、その解消法をご紹介しました。
働き方改革関連法案が施行されてから3年が経過しましたが、取り組みにゴールがあるわけではなく、より良い労働環境、より高い生産性のために継続的に取り組むべきものです。
仮に、現状は取り組みがうまくいっている企業でも、時間の経過とともに新たな問題点が生じる可能性は小さくないため、上記のような知識をもって長期的な視野で取り組んで行きましょう。
Concept Book
ローコード開発・業務プロセスのデジタル化で豊富な実績を持つintra-martが、お客様のビジネスにどのような効果をもたらすのか、特長や導入効果など製品コンセプトを詳しくご紹介しています。

お困りごとがありましたら、お気軽にご相談頂ければと思います。
















