社内アプリとは?導入するメリットや導入方法について解説

社内アプリとは、企業・組織が業務の効率化などを目的に導入する業務用アプリケーションです。社内アプリには、勤怠管理や情報共有、承認フローなどさまざまな機能を備えたものがあります。
とはいえ、「業務アプリを導入するメリットがわからない」「業務アプリの導入方法を知りたい」といった方も多いのではないでしょうか。
そこで本記事では、社内アプリとは何か、導入メリットや開発・導入方法、開発手順などを解説します。社内アプリの選定方法なども紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。
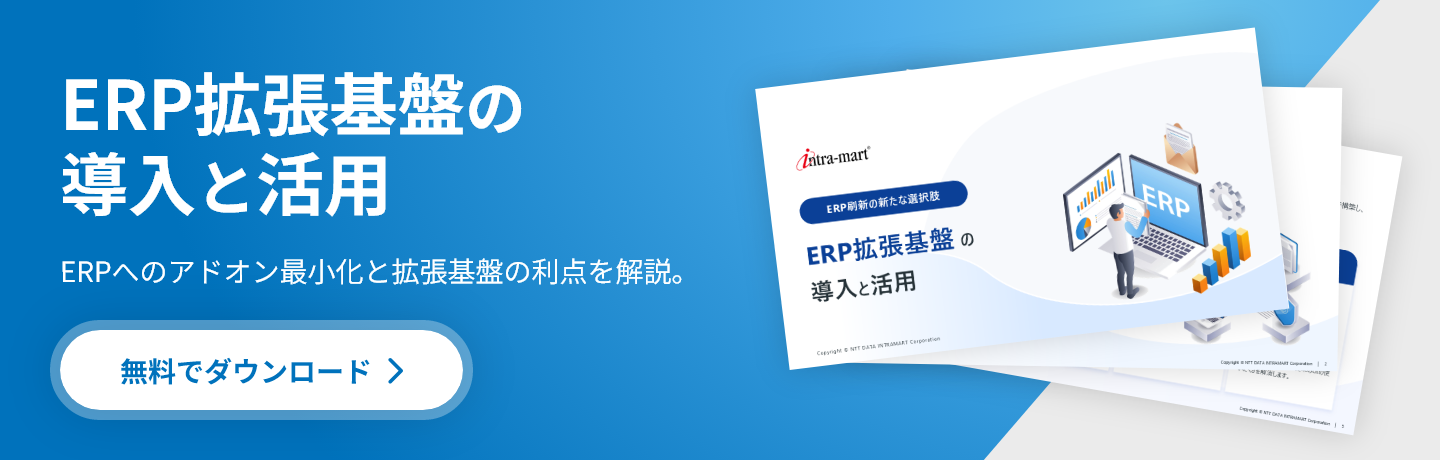
社内アプリとは
社内アプリとは、企業や組織が業務効率化や情報共有、コミュニケーションの円滑化を目的として導入する業務用アプリケーションのことです。これらは、従業員が日々の業務で使用するために設計されており、勤怠管理や社内チャット、申請・承認フロー、情報共有の掲示板などの機能を備えたものがあります。
かつては、Excelや紙ベースの運用が中心だった業務も、社内アプリの導入により、リアルタイムでの情報共有や自動化が可能となりました。とくに昨今のリモートワークやハイブリッド勤務の拡大により、場所や時間にとらわれず業務を進められる仕組みが必要とされ、社内アプリの重要性はますます高まっています。
また、社内アプリには業種や業務内容に応じて多様な形態があり、既製のパッケージ製品から自社独自に開発されたカスタムアプリ、さらにはノーコードツールを使って非エンジニアが作成する簡易アプリまで幅広く存在しています。
社内アプリを導入するメリット
社内アプリを導入する主なメリットは、以下の5点です。
・業務の効率化につながる
・データの一元管理ができる
・属人化の解消につながる
・コミュニケーションが活性化する
・柔軟な働き方が可能になる
それぞれのメリットについて詳しくみてみましょう。
業務の効率化につながる
社内アプリの最大のメリットは、業務効率の向上です。従来、複数のExcelファイルで管理していた情報や、紙ベースで行っていた申請業務を、アプリ化することで効率化が可能になります。たとえば、勤怠管理や経費精算などの定型業務は、ワークフローを自動化することで承認スピードが向上し、確認・再入力といった手間を省けるでしょう。
さらに、検索機能や通知機能、履歴の自動記録などが備わっているアプリであれば、必要な情報へ瞬時にアクセスでき、業務の停滞を防ぐことができます。部門間のやり取りがスムーズになり、全社的な業務最適化にもつながるでしょう。
データの一元管理ができる
社内アプリの活用により、複数部門や拠点に散らばっていた情報を一つのプラットフォーム上に集約することが可能になります。たとえば、顧客情報や案件進捗、会議資料などの共有をアプリで一元化することで、「どこに情報があるのか分からない」といった属人的な課題を解消することが可能です。
一元管理されたデータは、検索性や利便性だけでなく、データの正確性・最新性の維持にも貢献します。また、BI(ビジネスインテリジェンス)ツールや分析機能と連携することで、蓄積されたデータを可視化・分析し、経営判断に活かすことも可能です。
属人化の解消につながる
業務が特定の個人に依存してしまう「属人化」は、多くの企業で問題視されています。属人化が進行すると、担当者の不在時に業務が滞る、ノウハウが継承されないといったリスクが生じます。社内アプリを活用すれば、業務のフローや記録をアプリ内に残すことができるため、担当者が変わっても同じレベルで業務を遂行可能です。
また、マニュアルやナレッジ共有機能を組み込むことで、新人教育の効率化や、業務の標準化にも寄与します。結果として、組織全体の業務品質の底上げが期待できます。
コミュニケーションが活性化する
チャット機能や掲示板機能を持つ社内アプリを導入することで、従業員間のコミュニケーションが促進されます。部署を超えた情報共有や、社内全体への通知、意見の収集などを容易に行える環境が整い、組織全体の連携力を高めることが可能です。
とくにテレワークが進む中で、物理的に離れた場所にいる従業員同士が、リアルタイムで連絡を取り合える環境を整えることは、生産性やモチベーションの維持に不可欠です。アプリ内でのコミュニケーション履歴が残るため、後から内容を確認することもできます。
柔軟な働き方が可能になる
社内アプリは、スマートフォンやタブレット端末などのモバイルデバイスにも対応しており、場所や時間を問わず業務を遂行できる柔軟な働き方を実現します。外出先からの報告や、移動中の情報確認、在宅勤務時の勤怠管理などもスムーズです。
また、クラウドベースでの運用であれば、セキュリティを担保しつつ、どこからでもアクセス可能な環境を構築できます。これにより、多様なライフスタイルに合わせた働き方の実現や、従業員満足度の向上にも寄与するでしょう。
社内アプリの開発・導入方法
社内アプリの主な開発・導入方法には、以下の3つがあります。
・フルスクラッチ開発
・ノーコード開発
・パッケージアプリの利用
それぞれの開発・導入方法の概要をチェックしておきましょう。
フルスクラッチ開発
フルスクラッチ開発は、企業が自社の業務要件に完全に合わせてゼロからアプリを構築する方法です。この方法では、業務フローに沿った最適な設計が可能となり、独自の機能を持つアプリを構築できます。
さらに、UIやUXも自由に設計できるため、利用者のスキルや業務内容に最適化したインターフェースを実装できます。しかし、その自由度の高さは、開発コストと時間の増大というリスクとも表裏一体です。要件定義・設計・開発・テスト・運用・保守と全工程を外注・内製する必要があります。
また、運用後の改善や追加開発にも継続的なリソースが必要となるため、開発だけでなく長期運用におけるコストも事前に見積もっておくことが重要です。
ノーコード開発
ノーコード開発は、専門的なプログラミングスキルを持たない社員でも、アプリを作成できる手法です。近年のSaaSツールの進化により、社内の業務に合わせたアプリを数日〜数週間の短期間で構築可能になっており、業務現場のニーズに即座に対応できる点が大きな魅力です。
従来はIT部門に依頼していた軽微な機能追加やレイアウト変更も、業務部門で内製化することができ、開発スピードと柔軟性を大幅に向上可能です。
ただし、ノーコードには機能的な制約も存在し、大規模データの処理や複雑なロジックの実装には不向きな場合もあります。ガイドラインや運用ルールを整備し、統一的なUI設計や権限管理を行うことで、社内のノーコード開発を戦略的に活用することが求められます。
パッケージアプリ
パッケージアプリは、すでに市場で提供されている業務向けのアプリを導入する方式で、短期間かつ低コストでの導入が可能です。導入時点で多くの機能が完成しており、ユーザー教育や運用マニュアルも整備されていることが多いため、ITリテラシーの高くない組織でもスムーズに運用を開始できます。
一方で、パッケージアプリはあらかじめ用意された機能の枠内でしか動作しないことが多く、自社の業務にフィットしない場合は、カスタマイズ費用がかさんだり、業務のやり方をアプリに合わせる必要が生じる場合もあります。とくに複数のシステムを併用する場合、データの整合性や連携性に注意が必要です。
社内アプリを開発する際の流れ
社内アプリを開発する際の一般的な流れは以下のとおりです。
1.目的を決める
2.社内アプリに必要な機能を検討する
3.開発方法を選択する
4.開発・テストを行う
5.フィードバックを収集し改善を行う
開発の各ステップについてチェックしておきましょう。
目的を決める
社内アプリの開発において、最初に行うべきことは「なぜアプリを導入するのか」という目的の明確化です。目的が不明確なまま開発を進めてしまうと、機能が分散し、結果的に誰も使わないアプリになってしまうリスクがあります。ここで重要なのは、アプリが解決すべき課題を正確に把握し、それに基づいて目標を具体的に設定することです。
また、目的は1つに絞る必要はありませんが、複数ある場合は優先順位を明確にすることが大切です。優先すべき課題から着手し、段階的に機能を追加していくことで、無駄のない導入が可能になります。
社内アプリに必要な機能を検討する
目的が明確になれば、次はそれを実現するために必要な機能を洗い出します。機能検討の際は、現場の業務フローを整理し、「入力すべき情報」「処理方法」「出力・通知の形式」などを図示すると、必要な機能が自然と見えてくるでしょう。
この段階では「Must(必須)」「Should(できれば欲しい)」「Nice to have(あれば嬉しい)」の3分類で整理すると、開発の優先順位が付けやすくなります。また、将来的な拡張性も考慮し、後から追加可能な構造にすることも大切です。
開発方法を選択する
必要な機能が定まったら、次は「どう開発するか」を選ぶフェーズに入ります。以下の観点から、フルスクラッチ開発・ノーコード開発などのどの方法を採用するか検討しましょう。
・予算:大規模開発に十分な資金があるか
・導入スピード:いつまでにリリースすべきか
・業務の複雑さ:汎用機能で足りるか、カスタマイズが必要か
・ITリソース:自社に開発・運用できる人材がいるか
たとえば、短期間かつ低コストで導入したいのであればノーコード開発が有効です。一方、長期的に自社のビジネスにフィットさせたい場合は、フルスクラッチ開発が向いています。実際には、複数の手法を組み合わせて、ノーコードで開発した試作品をもとにフルスクラッチ化するケースもあります。
開発・テストを行う
開発段階では、まずプロトタイプ(試作版)を作成し、関係者に見てもらいながら仕様を調整していきます。これは「アジャイル型」と呼ばれる開発アプローチで、従来の「ウォーターフォール型」に比べて柔軟に機能修正ができるのが特徴です。
開発の中盤では、実装された機能が要件通りに動作するかを確認する「単体テスト」、複数機能を組み合わせて検証する「結合テスト」、さらに実際のユーザーによる「受け入れテスト」を実施します。ここで操作性や表示ミス、不具合などを徹底的に洗い出し、リリース前に解決しておくことが不可欠です。
また、社内ネットワーク環境やセキュリティポリシーとの整合性をチェックすることも重要です。たとえば、クラウド型アプリの場合、社外からのアクセスに制限があるか、通信は暗号化されているか、などをIT管理部門と協議する必要があります。
フィードバックを収集し改善を行う
社内アプリの導入は完成したら終わりではなく、むしろ導入後のフィードバックと改善が最も重要です。ユーザーが実際に業務で使う中で見えてくる課題や、「この機能が使いにくい」「もっとこうしてほしい」といった要望を収集し、それを次のバージョンで反映していくというサイクルを確立しましょう。
具体的には、定期的なアンケート・ミーティングでの意見聴取・アプリ内のフィードバックボタン設置などで声を集めます。ノーコードやローコード開発であれば、社内担当者が迅速に修正を反映できるため、業務に合わせた柔軟な運用が実現可能です。
さらに、利用状況のログ分析によって「使われていない機能」や「エラーが多い操作」を可視化し、潜在的な課題を見つけることも可能です。継続的な改善が進むほど、業務効率やユーザー満足度も向上し、社内アプリの価値が高まっていきます。
社内アプリを選定する際のポイント
社内アプリをパッケージアプリから選定する際のポイントは、主に以下の4点です。
・必要な機能がそろっているか
・操作性は良いか
・セキュリティ対策は万全か
・サポート体制は十分か
それぞれのポイントを詳しく確認しておきましょう。
必要な機能がそろっているか
まずは、必要な機能がそろっているかを確認しましょう。たとえば、勤怠管理を目的とするなら打刻・休暇申請・残業申請・シフト管理、情報共有なら掲示板・通知・ファイル添付・アクセス制限など、業務ごとに求められる機能は異なります。
ここで重要なのは、「ただ多機能であるか」ではなく、「自社の課題に対して必要な機能が揃っているか」です。多機能すぎるアプリは操作が煩雑になり、逆に使いづらさを招く場合もあります。そのため、事前に業務フローを整理し、必須機能・補助機能・不要機能を明確にしたうえで、比較検討を行うことが大切です。
また、業務の拡張や変化に備えて機能追加や連携が柔軟にできるかも確認しておくことも重要です。API連携や外部サービスとの連動、オプション機能の有無もチェックしておきましょう。
操作性は良いか
機能性が十分でも、操作性が悪ければ社内に定着せず、アプリの活用は進みません。とくに現場でのITリテラシーに差がある場合、誰にでもわかりやすいUI設計がされているか、直感的に操作できるかどうかが極めて重要です。
操作性は、トライアル版を実際に使用してみることで確認できます。可能であれば、実際の利用者層(現場社員や管理者など)にテストしてもらい、使いやすさや違和感を確認することを推奨します。
また、導入時の研修コストにも直結するため、操作の習得難易度は事前に把握しておくべきです。導入後すぐに運用できるか、マニュアルやヘルプが充実しているかも選定時に評価する必要があります。
セキュリティ対策は万全か
社内アプリは、従業員の個人情報や社外秘の業務データなど、企業にとって重要な情報を多く取り扱います。したがって、アプリのセキュリティ対策は非常に重要です。セキュリティレベルが低ければ、情報漏洩やサイバー攻撃のリスクを高め、企業の信用問題にも直結しかねません。
また、クラウド型アプリの場合は、データセンターの所在地・運用会社の信頼性・障害発生時の対応スピードなども確認すべきです。導入前にはベンダーに「セキュリティチェックリスト」や「脆弱性診断の実施有無」などを確認することをおすすめします。
自社が個人情報や機密情報を扱う業種(医療・金融・教育機関など)の場合は、業界ガイドラインに準拠しているかどうかも選定時の重要な評価軸です。
サポート体制は十分か
アプリの導入後、運用がスムーズにいくかどうかは「ベンダーのサポート体制」に大きく左右されます。トラブル時の対応スピードや質問への回答精度、継続的な改善提案の有無などが、運用ストレスや定着度を左右する主なポイントです。
とくに、自社にIT人材が少ない場合は、ベンダーによる技術サポート・操作トレーニングの有無は非常に重要です。
また、製品によっては定期的にアップデートや新機能の追加が行われます。その際に事前の告知や説明があるか、アップデートの影響を受けない運用設計が可能かどうかも、長期的な安心感につながるでしょう。
サポートの質は価格に比例するとは限らないため、実際の導入企業の口コミや、無料トライアル期間中の対応状況をチェックすることで、信頼できるパートナーを見極めることが大切です。
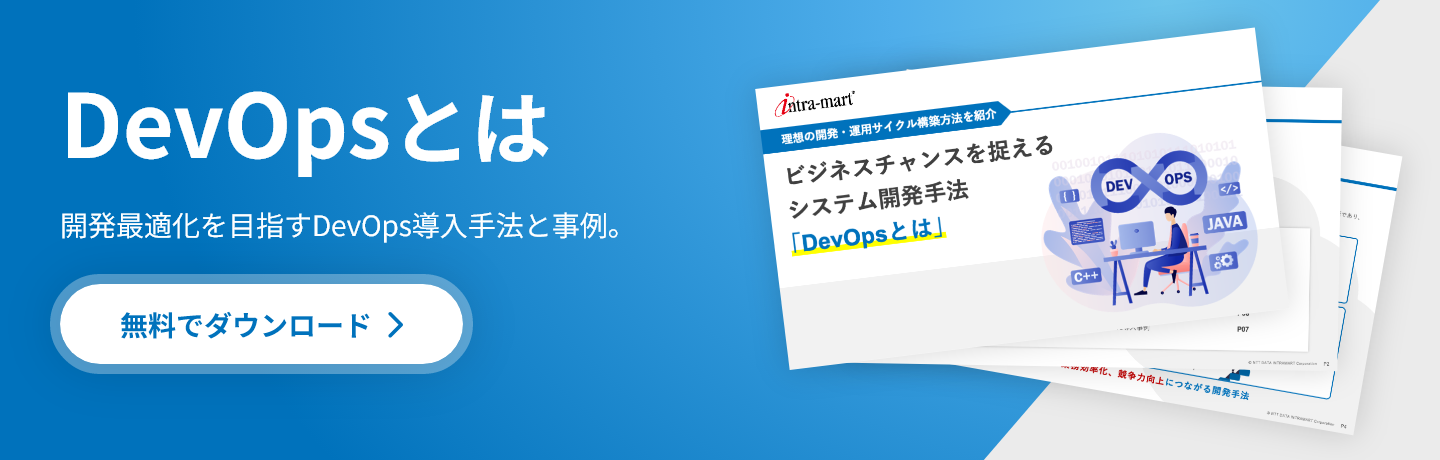
まとめ
本記事では、社内アプリとは何か、導入メリットや開発・導入方法などについて解説しました。社内アプリは、業務効率の向上や属人化の解消、柔軟な働き方の実現など、企業の生産性向上に直結するツールです。しかし、自社に合ったアプリを一から開発・運用していくには、機能要件の整理やシステムの連携、セキュリティ対策など、多くの課題が伴います。
社内アプリの導入を検討している場合は、「intra-mart(イントラマート)」がおすすめです。intra-martは、業務プロセスの可視化・自動化を実現するBPM(ビジネスプロセスマネジメント)機能と、柔軟な業務アプリをローコードで開発できる基盤を備えた、統合型の業務プラットフォームです。多様な業種・業務に対応できる拡張性の高さと、社内システムとの連携性にも優れており、数多くの企業で導入実績があります。
自社に最適な社内アプリの実現を目指すなら、ぜひintra-martの詳しい情報をチェックしてください。
Concept Book
ローコード開発・業務プロセスのデジタル化で豊富な実績を持つintra-martが、お客様のビジネスにどのような効果をもたらすのか、特長や導入効果など製品コンセプトを詳しくご紹介しています。

お困りごとがありましたら、お気軽にご相談頂ければと思います。
















