業務改善とは?進め方や注意点を解説

業務改善とは、企業などが業務のプロセスを見直し、効率的・効果的な形に再構築する取り組みです。業務改善により、業務効率や生産性の向上、コスト削減などさまざまなメリットが期待できます。
ただし、漠然と業務改善に取り組んでも期待どおりの効果が得られるとは限らないため、「業務改善とは具体的に何をすべきなのか知りたい」「業務改善の進め方がよくわからない」といった方も多いのではないでしょうか。
そこで本記事では、業務改善とは何か、実施メリットや進め方、注意点などを解説します。業務改善に役立つツールなども紹介するので、これから自社の業務改善に取り組む際にはぜひ参考にしてください。
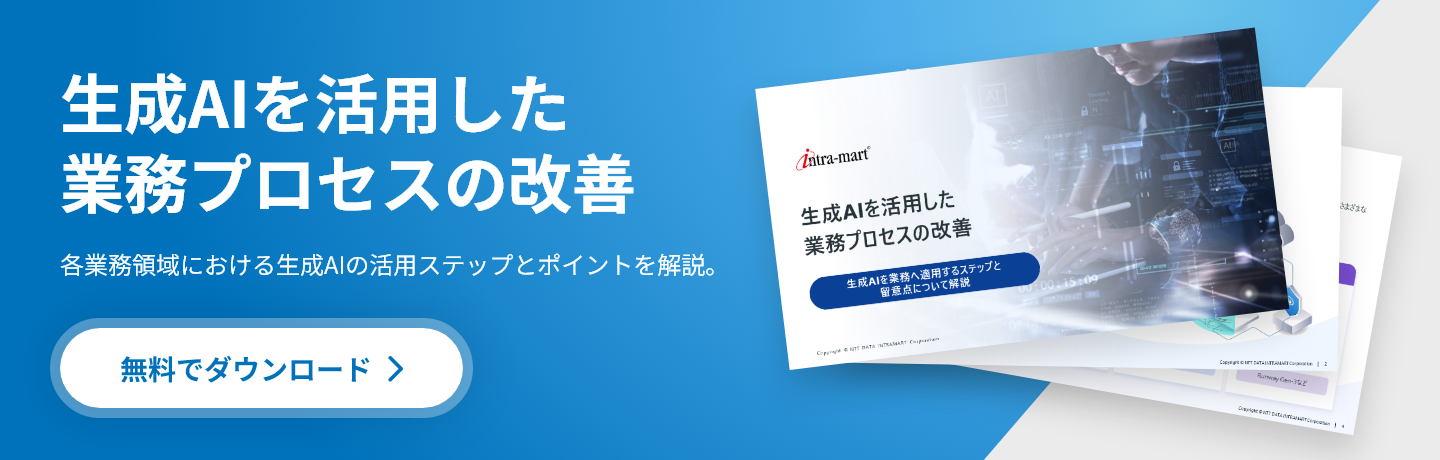
業務改善とは
業務改善とは、企業や組織内の業務プロセスを見直し、より効率的・効果的な形に再構築する取り組みのことです。具体的には、業務にかかる手間や時間を削減し、品質や成果の向上を目指すことを目的としています。
単なる一時的な対処ではなく、継続的な改善活動として、PDCA(Plan-Do-Check-Action)サイクルに沿って実行されるのが一般的です。
また、業務改善は大企業に限らず、中小企業や個人事業主にも必要な活動です。とくに近年では、DX(デジタルトランスフォーメーション)の流れを受けて、業務の自動化・デジタル化を通じた改善に注目が集まっています。現場主導で始める小さな改善から、全社的な改革まで、その規模やアプローチは多岐にわたります。
業務改善に取り組むメリット
業務改善に取り組む主なメリットは、以下の3点です。
・業務効率化・生産性向上
・コストの削減
・労働環境の改善
各メリットについて詳しくチェックしてみましょう。
業務効率化・生産性向上
業務改善の最大のメリットは、業務効率と生産性の向上にあります。日々の業務において、無駄な作業や重複業務、不要な確認・承認ステップが多く含まれているケースは少なくありません。こうした非効率を可視化し、適切に見直すことで、従業員が本来取り組むべきコア業務に集中できるようになります。
たとえば、紙による申請書類の提出を電子化するだけでも、印刷や提出、確認、保管にかかる手間を大幅に削減可能です。これにより、業務時間の短縮が図れ、従業員一人ひとりの生産性が向上します。
加えて、業務フローの標準化や自動化を進めることで、担当者ごとのバラつきがなくなり、品質の安定化にもつながります。これらは、結果として企業の競争力を高める要素となるでしょう。
コストの削減
業務改善はコスト削減にも直結します。たとえば、人的リソースの無駄遣いや時間の浪費、紙や備品などの物的資源の無駄といった、目に見えにくいコストを見直すことで、運営コストを抑えることが可能です。
また、業務改善により可視化されたコスト構造をもとに、より戦略的な予算配分が可能になります。単なる節約ではなく、無駄をなくして必要なところに集中投資することができるようになるのは、業務改善の大きなメリットです。
労働環境の改善
業務改善は、従業員の労働環境を整え、働きやすさを向上させるという観点からも重要です。非効率な業務が多く、長時間労働が常態化している職場では、従業員のストレスや不満が蓄積し、生産性の低下や離職率の上昇につながるリスクがあります。
改善によって、不要な作業が削減されることで残業時間が短縮され、業務の負担が軽減されます。
また、柔軟な勤務体系やテレワークの導入を推進する際にも、業務改善は不可欠です。タスクの可視化や進捗管理が仕組み化されていれば、物理的に離れた場所でも円滑な業務遂行が可能になります。
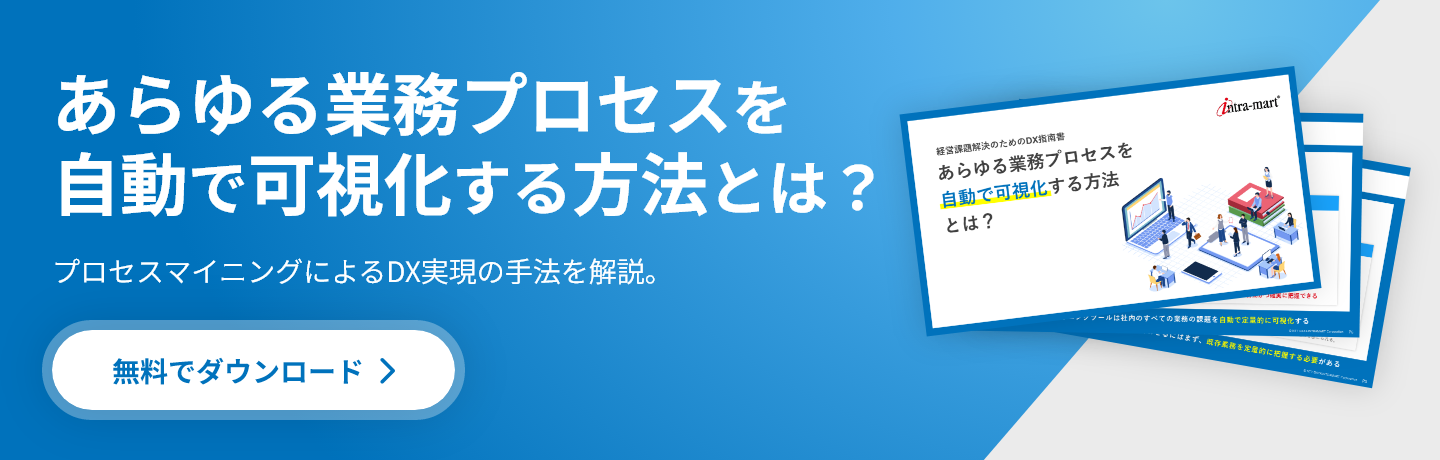
業務改善の進め方
業務改善は、一般的に以下のような流れで進めます。
1.現状の業務内容の可視化
2.課題・問題点を整理する
3.業務改善の計画を立てる
4.業務改善計画を実行する
進め方のそれぞれのステップでやるべきことをチェックしておきましょう。
現状の業務内容の可視化
業務改善の最初のステップは、現状の業務を把握し、可視化することです。これを怠ると、改善すべき点が曖昧になり、的外れな施策を打ってしまうリスクが高まるため注意しましょう。業務を可視化することで、誰が・何を・どのように行っているか、作業にどれだけ時間やコストがかかっているのかといった具体的な実態が明らかになります。
可視化の手法としては、業務フロー図・作業時間の記録・ヒアリング調査などがあります。現場で実際に業務を行っている従業員の声を聞くことも極めて重要です。実際の運用とマニュアルに記載されている手順が乖離しているケースもあるため、形式的な情報だけでなく、現場の実情を鑑みた情報収集が必要です。
このステップを丁寧に行うことで、改善対象の優先順位や、どのプロセスがボトルネックになっているのかが明確になり、次の段階での課題整理や施策立案がスムーズになります。
課題・問題点を整理する
業務の実態を把握したら、次はその中でどの業務に課題があるのか、どの工程がボトルネックになっているのかを整理しましょう。
たとえば、同じデータを複数のシステムに二重入力している、紙ベースの業務で情報の伝達に時間がかかっている、承認プロセスが多段階すぎて処理が滞る、といったものは典型的な改善対象です。
ここでは、問題点を「人」「物」「情報」「方法」「環境」などのカテゴリに分類し、原因を深掘りすることが重要です。
業務改善の計画を立てる
課題が明確になったら、それを解決するための改善計画を立てましょう。ここでは「どの業務を・どのような手法で・いつまでに・誰が改善するか」といった具体的な内容を定めることが求められます。
改善案は、必ずしもシステム導入や大規模改革である必要はありません。小さな改善であっても、現場の業務に即した内容であれば大きな効果をもたらします。むしろ、最初から大掛かりな改善を狙うと、計画倒れになるリスクも高まるため要注意です。
改善案には、以下のような視点を取り入れると効果的です。
| 業務改善手法 | 例 |
| 業務の自動化 | RPAの導入 |
| ワークフローの短縮 | 承認プロセスの簡略化 |
| 情報の一元化 | クラウドストレージの活用 |
| ツールの導入・切替 | チャットツール、SFA |
また、改善施策は「KPI(重要業績評価指標)」を設定し、効果の測定ができるようにしましょう。KPIの例としては、業務時間の短縮率、ミス発生件数の減少、顧客対応スピードの向上などが挙げられます。
業務改善計画を実行する
計画を立てたら、いよいよ実行段階です。ここでのポイントは、関係者全員の理解と協力を得ることです。改善案を現場に押し付ける形で進めると、形だけの実行に終わり、形骸化してしまう恐れがあります。
実行前には、改善の目的や期待される効果を丁寧に説明し、現場の意見や懸念を共有・解消する機会を設けましょう。また、導入するツールや新しい業務フローがある場合は、十分な教育やマニュアル整備が不可欠です。
さらに、実行中は定期的に進捗を確認し、柔軟に対応を調整することが重要です。トライアル導入や一部部署での試験運用から始めて、効果を見ながら全社展開します。
業務改善を進める際の注意点
業務改善を進める際の注意点としては、主に以下の3つが挙げられます。
・全社的に取り組む
・優先順位を付けて段階的に取り組む
・振り返りを行う
各注意点をチェックして、自社の業務改善に活かしてください。
全社的に取り組む
業務改善を成功させるには、一部門だけでなく全社的な視点を持つことが不可欠です。特定の部署だけで改善を進めると、その部門内では効率化が進んでも、他部門との連携がうまくいかず、かえって非効率になることがあります。業務は多くの場合、部門をまたいで連動しているため、一部だけを改善しても全体の最適化にはつながりません。
また、現場から経営層まで、階層を超えた協力体制が必要です。経営層が業務改善の意義を正しく理解し、方針を明確に示すことで、組織全体に統一感のある取り組みが可能になります。逆にトップが業務改善に関心を示さない場合、現場は動きづらく、改善活動が浸透しません。
さらに、部門間の壁を超えて情報共有し、改善の進捗や効果を見える化することも大切です。社内ポータルや定期会議を活用し、成功事例を横展開していく文化を育てることで、全社的な改善活動が定着します。
先順位を付けて段階的に取り組む
業務改善は一気にすべてを見直すのではなく、優先順位をつけて段階的に取り組むのが成功のためのポイントです。業務改善に取り組む際、一度にすべてを改善しようとすると、リソースが分散してしまい、かえってどれも中途半端になる可能性があります。
改善対象を選定する際には、「効果が大きい業務」「頻度が高い業務」「改善後のインパクトが明確な業務」などを優先するのが基本です。初期段階では、小さな成功体験を積み上げることが重要であり、実現可能性の高い業務から着手することで、関係者の納得感と協力を得やすくなります。
また、業務改善の実行にあたっては、必要なリソース(人材・予算・時間)を適切に見積もるとともに、スケジュール管理も慎重に行う必要があります。1つの改善施策が完了してから次に進むことで、改善の効果検証と修正が容易になるでしょう。
振り返りを行う
業務改善はやりっぱなしにせず、必ず振り返り(レビュー)を実施することが不可欠です。実施した施策に対して、計画通りに実行されたか、目標としていた効果が得られたかを確認し、得られた成果と課題を洗い出します。
振り返りは改善活動のPDCAサイクルの「Check(評価)」と「Act(改善)」に該当するものであり、ここでの学びを次の改善活動に活かすことが、継続的な業務改善には欠かせません。
評価の指標には、KPIを用いることで定量的な評価が可能です。例えば、「業務処理時間が〇%短縮された」「ヒューマンエラーが〇件減少した」といった具体的な数値をもとに振り返ることで、成果が明確になり、関係者の納得も得やすくなります。
また、現場の声も積極的に収集し、「実際に使ってみてどうだったか」「新たな課題が出てきていないか」など、定性的な評価も取り入れることで、次のアクションの質を高めることができます。
業務改善に活用できるツール
業務改善に活用できるツールとして、以下の6つを紹介します。
・マニュアル作成ツール
・プロジェクト管理ツール
・クラウドストレージ
・コミュニケーション・チャットツール
・RPA
・SFA
各ツールの機能を把握したうえで、導入を検討してみてください。
マニュアル作成ツール
業務を標準化・可視化するうえで欠かせないのが、マニュアル作成ツールです。マニュアルは従業員が業務を正確に理解・遂行するための道標であり、属人化の防止・ミスの削減・新人教育の効率化などに直結します。
従来のマニュアルは紙ベースで煩雑だったり、更新が滞ったりしがちでしたが、デジタルツールの活用により、効率よく作成・共有・更新が可能になりました。一部のマニュアル作成ツールは、画像や動画を用いた視覚的な手順共有を可能にし、誰でも直感的に操作できるインターフェースを備えています。
また、こうしたツールはクラウドベースで運用できるものも多く、常に最新版を共有できるという利点もあります。業務改善の第一歩として作業の標準化や教育の仕組み化を目指す企業にとって、導入効果の高いツールといえるでしょう。
プロジェクト管理ツール
業務改善の取り組みを計画的に推進するには、プロジェクト管理ツールの導入が効果的です。業務は複数部署や関係者を巻き込んだタスクの集合体であり、誰が・いつまでに・何をするのかを明確にしないと、実行段階で混乱や遅延が発生します。
多くのプロジェクト管理ツールでは、タスクの可視化・進捗管理・担当者の割り当て・期限設定・ファイル共有などを一元的に行えます。これにより、チーム全体で共通認識を持ちながら業務を進めることができ、抜け漏れや手戻りを防ぐことが可能です。
また、プロジェクトの実行後にはログやデータをもとに振り返りや改善も行えるため、PDCAサイクルの運用にも適しています。
クラウドストレージ
クラウドストレージは、業務で扱う膨大なファイルやデータを効率よく保管・共有・管理するために活用されるツールです。従来のように社内サーバーやメールでのやり取りに依存することなく、インターネット環境があればどこからでもアクセス可能な点が大きな特徴です。
一般的なクラウドストレージは、ファイルの共同編集・アクセス権限の細分化・変更履歴の確認・バージョン管理など、柔軟で安全な情報共有が可能です。業務改善においては、書類探しの時間削減や重複作業の防止、セキュリティ強化といった効果が見込まれます。
とくにテレワークや外出の多い職種では、どこでも必要な資料にアクセスできる環境は、業務のスピードと質を大きく向上させます。
コミュニケーション・チャットツール
業務改善を効果的に進めるには、社内コミュニケーションの活性化が不可欠です。その手段として注目されているのが、ビジネスチャットなどのコミュニケーションツールの導入です。従来のメールに比べて即時性が高く、やり取りの履歴も残るため、情報の伝達・共有が円滑になります。
主要なコミュニケーション・チャットツールは、グループチャット・ファイル共有・スレッド管理・通知設定など多機能かつ拡張性の高い構成です。部署横断のプロジェクトでもリアルタイムに状況を共有できるため、確認・報告・相談のスピードが飛躍的に向上します。
業務改善の観点では、「情報の属人化防止」「会議の削減」「意思決定の迅速化」などの成果が得られやすく、全社的な生産性の向上に寄与します。さらに、プロジェクト管理ツールや他の業務アプリと連携することで、より高い効果が期待できるでしょう。
RPA
RPA(Robotic Process Automation)は、定型的で繰り返しの多い業務をソフトウェアロボットにより自動化するツールで、近年の業務改善手段として注目を集めています。たとえば、請求書の転記作業、受注データのシステム入力、Webサイトからの情報収集など、人が行っていた事務作業を代行可能です。
代表的なRPAツールには、非エンジニアでも使えるノーコード・ローコード設計の製品が増えています。ルールベースの単純作業であれば、RPAに置き換えることでヒューマンエラーを防止し、処理速度も大幅に向上します。
RPAの導入は、業務時間の短縮・人件費の削減・業務品質の安定化など、複数の面で改善効果をもたらします。とくに人手不足や業務過多に悩む現場では、業務の自動化によって余剰リソースを生み出し、より創造的な仕事へシフトできる土台を築ける点が大きな魅力です。
SFA
SFA(Sales Force Automation)は、営業活動を効率化・見える化するためのツールで、営業部門における業務改善には欠かせない存在です。SFAを活用すれば、顧客との接点情報・商談履歴・案件の進捗状況などを一元管理し、属人化しがちな営業ノウハウを全社で共有できます。
SFAによって営業プロセスを可視化することで、どの営業活動が成果につながっているかを定量的に分析でき、個人やチームのパフォーマンス改善が可能です。
また、SFAはMA(マーケティングオートメーション)やCRM(顧客管理システム)と連携することで、顧客獲得からクロージング、アフターフォローまでの一連のプロセスを統合的に管理できます。これにより、より戦略的で再現性のある営業活動が可能となり、営業組織全体の底上げにも貢献するでしょう。
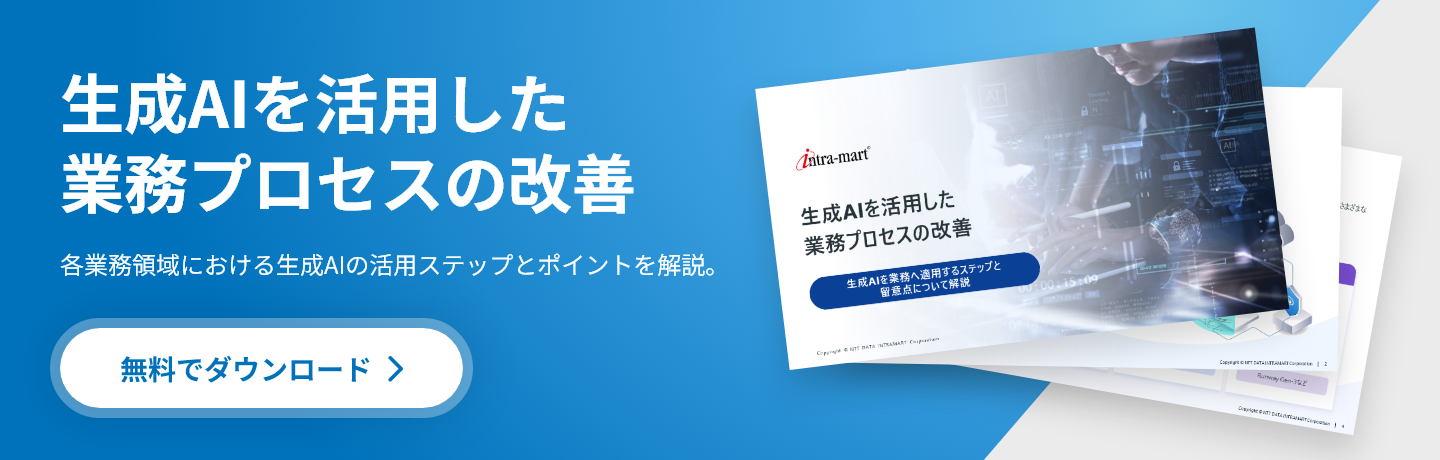
まとめ
本記事では、業務改善とは何か、メリットや進め方などを解説しました。業務改善は、単なる作業の効率化にとどまらず、企業全体の生産性向上やコスト削減、働き方改革の推進、従業員満足度の向上にも大きく貢献する取り組みです。
しかし、効果的な改善を実現するためには、現状の業務の可視化から課題の特定、計画の立案と実行、さらに定期的な振り返りまで、一貫したプロセス管理が求められます。また、各工程を支えるツールの選定も重要であり、業務ごとに最適な仕組みを導入することが成功の鍵となります。
こうした課題の解決には、業務プロセスの設計から業務アプリ開発、自動化・デジタル化までをトータルに支援する統合プラットフォーム「intra-mart(イントラマート)」がおすすめです。豊富な機能と柔軟なカスタマイズ性により、部門単位から全社的な業務改善まで幅広く対応可能で、多くの企業で成果を上げています。
業務改善に取り組みたい方は、ぜひintra-martの詳しい情報をチェックしてください。
Concept Book
ローコード開発・業務プロセスのデジタル化で豊富な実績を持つintra-martが、お客様のビジネスにどのような効果をもたらすのか、特長や導入効果など製品コンセプトを詳しくご紹介しています。

お困りごとがありましたら、お気軽にご相談頂ければと思います。
















