業務プロセス改善の進め方や成功させるポイントを解説

業務プロセスの改善は、業務の効率化やリスクマネジメントなどに欠かせない取り組みです。近年、急速に広まっているDXの促進とも、業務プロセスの改善は深く関係しています。
しかし、業務プロセスの改善は全社を巻き込む大きなプロジェクトとなるケースもあるため、「業務プロセス改善の目的やメリットを確認したい」「業務プロセス改善の進め方を知りたい」という方も多いのではないでしょうか。
そこで本記事では、業務プロセス改善のメリットや進め方について解説します。業務プロセス改善を成功させるためのポイントも紹介するので、ぜひ最後までチェックしてください。
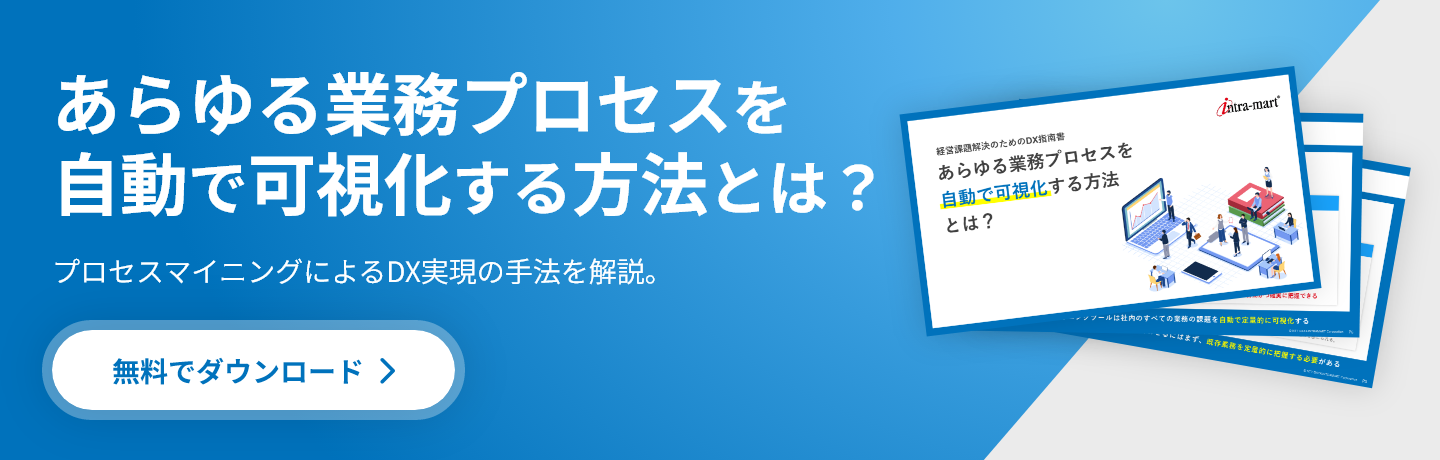
業務プロセスとは
業務プロセスとは、企業や組織の目標を達成するために行われる一連の業務や作業の流れのことです。たとえば「商品を仕入れて販売する」「顧客から問い合わせを受けて対応する」「請求書を発行して入金を確認する」といった流れが、業務プロセスに該当します。多くの場合、複数の部門や担当者が関与するため、個々の業務だけでなく、それらをどう連携させるかも重要なポイントです。
業務プロセスは、「インプット(入力)」「プロセス(処理)」「アウトプット(出力)」の3要素から構成されます。たとえば、顧客情報を入力し、社内システムで契約処理を行い、契約書を出力するような流れがその一例です。このように、業務プロセスは企業活動の根幹を担っており、その品質やスピードが企業全体のパフォーマンスに大きく影響を与えます。
とくに近年では、競争環境の激化や労働力不足、デジタル化の進展などを背景に、業務プロセスの見直しや最適化が求められる場面が増えています。業務プロセスを定義・整理することは、業務の無駄を省き、効率的な体制を構築するための第一歩といえるでしょう。
業務プロセス改善の目的
業務プロセスを改善する主な目的としては、以下の3点が挙げられます。
・業務の無駄や非効率を排除することによる生産性向上
・ヒューマンエラーの削減と品質の安定化
・経営判断のスピードと正確性の向上
まずは、各目的についてチェックしておきましょう。
業務の無駄や非効率を排除することによる生産性向上
業務プロセス改善の最大の目的は、日々の業務に潜む無駄を排除し、生産性を向上させることです。手書きとシステム入力の二重処理・紙ベースの承認フローなど、非効率な業務を見直して業務を簡素化・自動化することで、時間やコストの削減だけでなく、従業員が本来注力すべき業務に集中できる環境を整えることが可能です。
ヒューマンエラーの削減と品質の安定化
属人的な業務や曖昧な手順に依存していると、ミスや処理のバラつきが起きやすくなります。業務プロセスを標準化・マニュアル化することにより、誰が担当しても一定品質を保てる体制を構築可能です。加えて、承認フローやチェック体制の明確化、RPAなどの自動化ツールの導入により、人の手によるミスを減らすことができます。
経営判断のスピードと正確性の向上
業務プロセスの整備によって、必要な情報がリアルタイムで共有されるようになれば、経営層や管理職による判断も迅速かつ正確になります。たとえば営業活動の進捗や在庫状況、コストの状況などを即座に把握できるようになれば、変化の早い市場においても柔軟な戦略判断が可能です。
業務プロセスを改善するメリット
業務プロセスを改善するメリットとしては、主に以下の3点が挙げられます。
・業務効率化
・リスクマネジメント
・DXの促進
それぞれのメリットについてチェックしておきましょう。
業務効率化
業務プロセスの改善は、無駄や重複作業を排除することにつながり、業務の効率化を実現します。たとえば、紙ベースで行っていた承認フローを電子化したり、複数のシステムに同じ情報を二重入力していた業務を統合することで、業務時間を大幅に短縮可能です。
業務が効率化されることで、従業員はより重要なコア業務に集中できるようになり、生産性も改善します。
また、業務の流れが整理されることで、引き継ぎや教育がしやすくなり、属人化の解消にも効果があります。誰が業務を担当しても一定の水準で処理が行える体制が整えば、業務の安定性も高まるでしょう。
リスクマネジメント
業務プロセスの明確化と改善は、企業にとってのリスク低減にも直結します。曖昧な業務フローや個人依存の処理手順は、ミスや抜け漏れの温床となり、場合によってはクレームや法令違反といった深刻な問題に発展しかねません。
プロセスを見直し、標準化・自動化を進めることで、ヒューマンエラーの発生リスクを抑えると同時に、業務の監査性も向上します。また、内部統制やコンプライアンスの強化といった観点からも、業務プロセス改善は極めて有効な施策です。
さらに、業務の流れが可視化されていれば、非常時や緊急時の代替対応が取りやすくなり、BCP(事業継続計画)の観点でも大きな意義を持ちます。
DXの促進
業務プロセスの改善は、DX(デジタルトランスフォーメーション)推進の土台にもなります。DXは単なるITツールの導入ではなく、業務の在り方そのものを、デジタルを前提に見直す取り組みであり、その第一歩として業務プロセスの可視化・再構築が不可欠です。
アナログな業務や手作業が多く残っている状態では、DXは単なる部分的なデジタル化にとどまり、組織全体の変革には至りません。プロセスを見直すことで、ツールの導入意義や効果も明確になり、導入後の定着・活用がスムーズになります。
また、業務プロセスをデジタル基盤に載せることで、データの収集・分析が可能となり、経営判断のスピードや精度も向上します。業務プロセス改善は、単なる効率化にとどまらず、企業の競争力強化や新たな価値創出にもつながる重要な取り組みです。
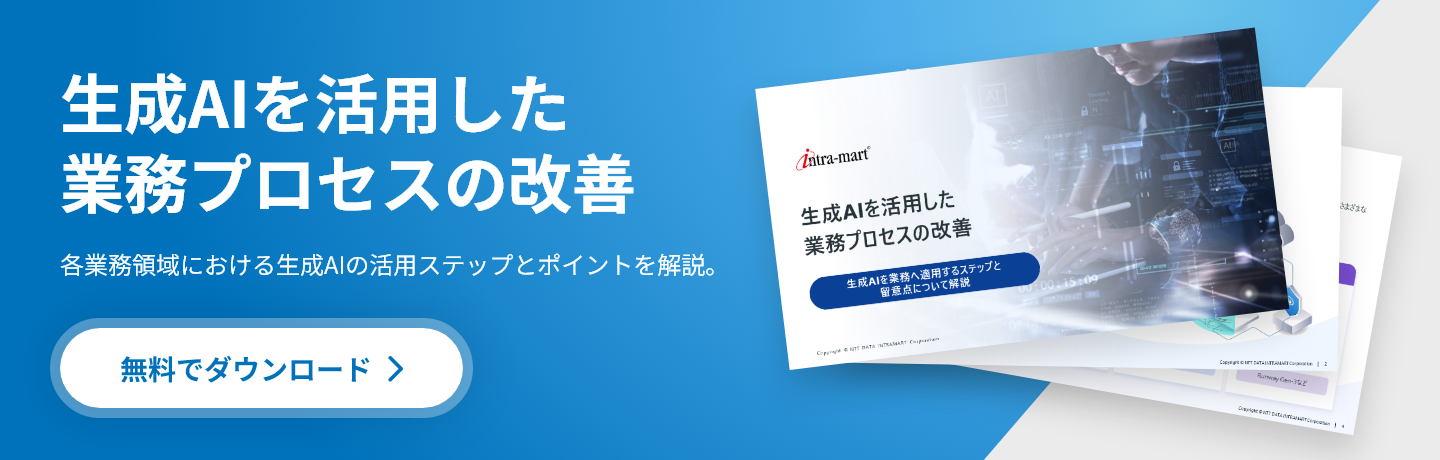
業務プロセス改善の進め方
業務プロセスの改善は、一般的に以下のような進め方で行われます。
1.現状を把握・分析する
2.課題を整理し優先順位を決める
3.改善案を策定する
4.改善案を実施する
5.評価と改善を行う
各ステップについて、何をすべきかを確認しておきましょう。
現状を把握・分析する
業務プロセス改善の最初のステップは、現場で実際に行われている業務内容やその流れを正確に把握し、分析することです。改善の対象を誤ってしまえば、効果的な改革にはつながりません。まずは「誰が」「何を」「いつ」「どこで」「どのように」行っているのかを洗い出すことが重要です。
定量的なデータ(作業時間・頻度・工数など)と、現場のヒアリングを併用することで、実態とのギャップも明らかになります。
また、単にフローを図にするだけでなく、業務に内在する非効率や属人化の度合い、手戻り発生の頻度など、課題の兆候を細かく拾い上げておくことが大切です。
課題を整理し優先順位を決める
業務の現状把握をもとに、次に行うべきは課題の特定と整理です。ここでは、業務の中で何が問題なのか、どこに非効率やエラーの原因があるのかを論理的に洗い出します。たとえば「対応に時間がかかる」「入力ミスが頻発する」「判断に個人差がある」といった声は、課題の発見につながる貴重なヒントとなるでしょう。
課題を整理する際には、「人」「手順」「情報」「システム」「環境」といったカテゴリで分類し、どの要因が課題を引き起こしているのかを明確にします。さらに、課題ごとに影響度と発生頻度をスコア化すると、客観的な優先順位付けがしやすくなります。
優先順位をつける際は、業務への影響の大きさだけでなく、改善に必要な工数や費用も考慮し、最小の投資で最大の成果が得られるポイントから着手するとよいでしょう。
改善案を策定する
課題の特定と優先順位の整理が終わったら、次に実施すべきは改善案の策定です。ここでは、課題をどう解決するかを具体的なアクションとして落とし込むことが求められます。改善案には、大規模なシステム導入から、手順の簡素化やチェックリストの追加といった小規模な施策まで多様な選択肢が存在します。
重要なのは、「改善案が現場の実情に合っているか」という点です。業務改善の失敗事例では、「理想を追い求めすぎた結果、現場が混乱し、逆に非効率が増す」というケースも見られます。改善案の策定には、関係部署を巻き込み、現場の声を反映したうえで現実的かつ段階的に実行可能な内容にすることが大切です。
また、改善策ごとに「目的」「対象範囲」「実施時期」「担当者」「必要なツール・予算」などを明文化し、計画書の形にしておくと、後の運用や評価がスムーズに進みます。さらに、施策の効果を測定するためのKPI(例:作業時間の短縮率、エラー件数の削減率など)を事前に設定しておくことで、実施後の評価も客観的に行えるでしょう。
改善案を実施する
改善案を策定したら、次はいよいよその実行段階に入ります。実行フェーズでは、単に計画を開始するだけでなく、「改善の狙いや意義」を関係者にきちんと伝えることが極めて重要です。とくに現場の担当者にとっては、業務フローや手順の変更は大きなストレスになる場合もあり、しっかりとした説明と納得感がないと、形だけの改善に終わってしまいます。
導入前には、変更点や新しい業務フローをマニュアルや図解でわかりやすく共有し、必要に応じて研修やトレーニングを行いましょう。ITツールの導入が含まれる場合は、システム部門や外部ベンダーとの連携も欠かせません。
また、いきなり全社導入するのではなく、まずはスモールスタートを行い、一定の効果や現場のフィードバックを収集したうえで、本格展開するのがリスクを最小限に抑える方法です。導入期間中はプロジェクト管理ツールなどを活用し、進捗状況の可視化と課題の即時共有ができる体制を整えることもポイントです。
評価と改善を行う
業務プロセスの改善は、実行して終わりではなく、評価とさらなる改善のサイクル(PDCA)を回していくことで成功につながります。実施した改善施策が、実際にどれだけの効果を上げたか、計画通りに運用されているかを定期的にモニタリングし、定量・定性の両面からの検証が必要です。
同時に、現場担当者からのヒアリングやアンケートを通じて、使い勝手や運用上の課題を拾い上げることも重要です。
もし効果が限定的だった場合でも、その要因を明確にし、再度改善策を立案していくことが継続的な改善の基本です。また、改善活動が成果を上げた場合は、社内でその事例を共有・展開し、他部門への横展開を進めることで、組織全体のプロセス最適化が進みます。
業務プロセス改善を成功させるポイント
業務プロセス改善を成功させるポイントとしては、以下の3点が挙げられます。
・業務プロセスを可視化する
・ツールやシステムを活用する
・継続的に改善を続ける
各ポイントの詳細をチェックして、自社の業務プロセス改善に活かしてみてください。
業務プロセスを可視化する
業務プロセス改善を成功させるうえで、最も基本かつ重要なポイントは「可視化」です。業務の流れがブラックボックス化していると、どこに課題があるのかを正確に把握することができず、改善の方向性も曖昧になります。業務の全体像と各工程のつながりを視覚的に整理することで、非効率な部分やボトルネックが明確になり、具体的な改善施策を立案しやすくなるでしょう。
「誰が」「いつ」「どこで」「どのような業務を行っているか」を見える化することで、複数の部門が関与する業務でも、役割や責任が明確になります。
ツールやシステムを活用する
業務プロセス改善を手作業のみで進めるには限界があります。作業の可視化・業務フローの設計・タスクの進捗管理・改善の実行・結果の測定など、さまざまな工程を支えるためには、適切なツールやシステムの導入が不可欠です。
たとえば、業務の進捗を管理するには「プロジェクト管理ツール」、業務の標準化と教育には「マニュアル作成ツール」、業務の自動化には「RPA」が活用されます。クラウドストレージやビジネスチャットも、情報共有やリアルタイム連携の基盤として非常に有効です。
また、近年では業務プロセス管理に特化した「BPM(Business Process Management)ツール」や、ノーコードでアプリを作成できる「ローコード開発プラットフォーム」も注目されています。これらを活用することで、業務改善をよりスピーディに、しかも現場主導で進めることが可能です。
継続的に改善を続ける
業務プロセス改善は、一度の施策で完結するものではありません。むしろ、継続的に改善活動を繰り返し、業務の質と効率を少しずつ高めていく文化を組織に定着させることが、本質的な成功といえるでしょう。その意味で、業務改善はプロジェクトではなく継続的な経営活動の一環と捉える必要があります。
継続的改善の代表的なフレームワークとしては、「PDCA(Plan-Do-Check-Act)サイクル」があります。「業務プロセスの見直し→改善案の策定→実行→評価→再改善…」というサイクルを一定のリズムで回すことで、組織全体の業務レベルが少しずつ上がっていきます。
また、「KPIの定期モニタリング」「月次の業務レビュー」「現場からのボトムアップ提案制度」など、改善のための仕組みを社内に組み込むことも有効です。とくに現場からのフィードバックを吸い上げ、即時に反映できる体制があれば、変化への対応力も高まり、柔軟で強い業務体制が構築されます。
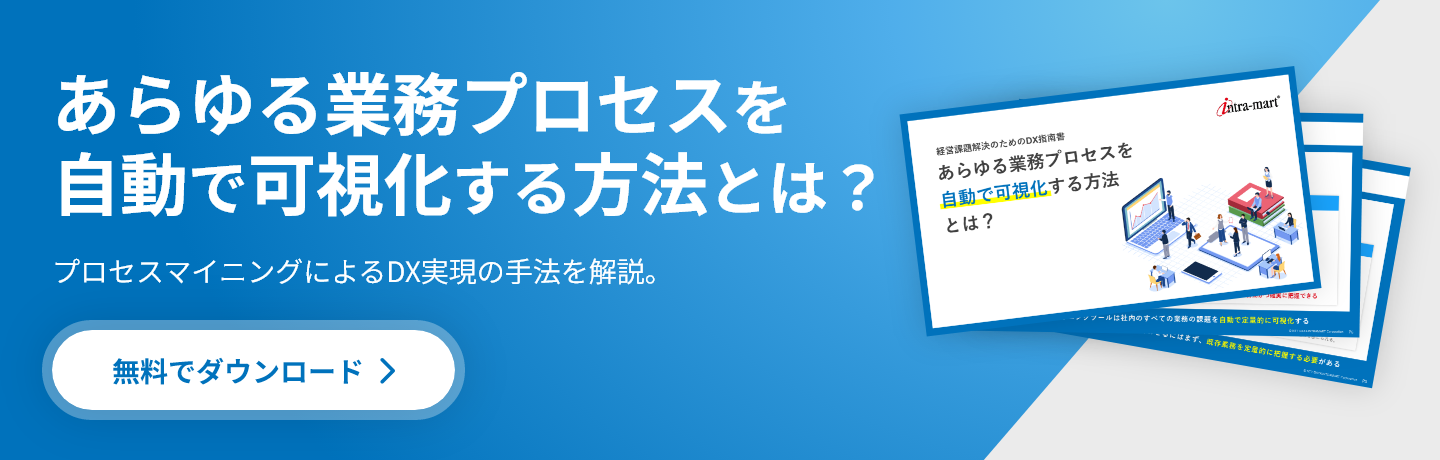
まとめ
本記事では、業務プロセス改善について、メリットや進め方、成功させるためのポイントなどを解説しました。業務プロセスの改善は、企業が持続的に成長するための重要な施策です。単なる業務の効率化にとどまらず、組織の課題可視化・業務品質の向上・顧客満足度の向上・柔軟な経営体制の構築へとつながります。
しかし、業務プロセスの改善は一朝一夕で完了するものではなく、継続的な取り組みと仕組みの定着が求められます。その実現には、改善活動の設計から業務の可視化・アプリ開発・ワークフロー管理・データ分析までを一気通貫で支援する統合プラットフォーム「intra-mart(イントラマート)」がおすすめです。
intra-martは、業務プロセスの標準化・効率化・自動化を強力に支援するBPM(Business Process Management)プラットフォームで、あらゆる業務に柔軟に対応できる開発基盤と豊富な機能を備えています。ノーコード・ローコード開発にも対応し、現場主導での改善活動をスピーディに実現可能です。
業務プロセス改善を本格的に進めたい企業の方は、ぜひintra-martの詳しい情報をチェックしてください。
Concept Book
ローコード開発・業務プロセスのデジタル化で豊富な実績を持つintra-martが、お客様のビジネスにどのような効果をもたらすのか、特長や導入効果など製品コンセプトを詳しくご紹介しています。

お困りごとがありましたら、お気軽にご相談頂ければと思います。
















