ローコード開発・ノーコード開発の違いは?導入の注意点も紹介

ローコード開発とノーコード開発の違いは、ローコード開発が可能な限りソースコードを書かず必要最小限のプログラミングを行ってアプリケーション開発を行う手法であるのに対し、ノーコード開発ではまったくソースコードを書かずに開発が行えるという点です。
通常は、数ヵ月から数年単位の時間がかかるアプリケーション開発を大幅に短縮できる開発手法として注目を浴びている「ローコード開発」「ノーコード開発」。厳密には両者に違いがありますが、どちらも直観的に操作できるGUIを利用して直観的な操作で開発が行える点がメリットです。
本コラムでは、ローコード開発、ノーコード開発それぞれのメリット・デメリットや、開発ツールを導入する時の注意点などをご紹介いたします。
【関連記事】
ローコード開発ツール・プラットフォーム17種を比較!おすすめのツールは?
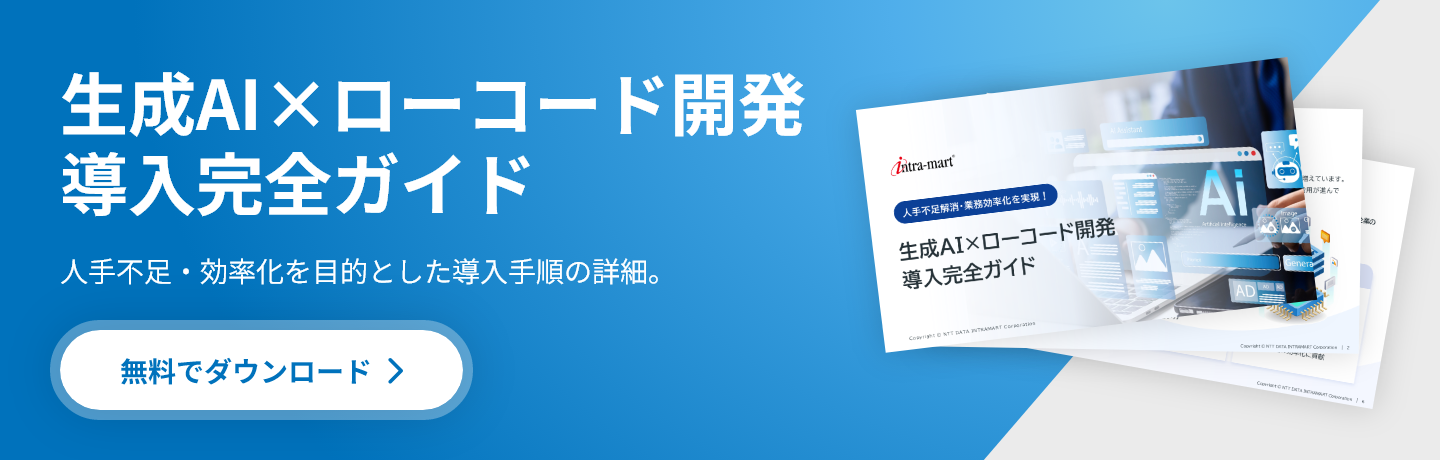
1. ローコード開発、ノーコード開発とは?
ローコード開発、ノーコード開発とはそれぞれどのような開発手法なのでしょうか?
ローコード開発とは?
ローコード開発(Low-Code development)とは、最低限、必要なソースコードのみを書き、それ以外は、GUI(Graphical User Interface/グラフィカルユーザインタフェース)とよばれる、視覚的に理解できて直感的に操作できる画面を用いて、あらかじめ用意された機能単位を組み合わせることでアプリケーション開発が行える開発手法のことです。
ローコード開発について詳しくは、下記の記事もご覧ください。
【関連記事】
ニューノーマルのDXを支える注目トレンド「ローコード開発」とは
ローコード開発ツール・プラットフォーム17種を比較!おすすめのツールは?
ノーコード開発とは?
ノーコード開発(No-Code development)とは、名前の通り、まったくソースコードを書かずにアプリケーション開発を行う手法のことです。ローコード開発と同様、あらかじめ用意された機能単位を、GUIを活用して、ドラッグアンドドロップといった直観的で簡単な操作のみで開発できます。まったくソースコードを書かないため、ローコード開発に比べると自由度は下がります。
2. ローコード開発、ノーコード開発が注目される背景
ローコード開発、ノーコード開発は、以前から存在していましたが、近年、注目を浴びているのには、働き方改革やデジタルトランスフォーメーション(DX)の促進などがあります。
政府が働き方改革を打ち出した背景の一つには、少子高齢化による将来的な人口減が予測され、その影響で労働人口も減少してしまうことがあります。少ない労働人口で資本を拡大していくためには、業務効率化や生産性向上が求められます。
DX推進の背景には、老朽化するレガシーシステムの保守にコストがかかり過ぎることや、IT人材不足の懸念、最新のデジタルテクノロジーの登場によって既存の市場が陳腐化するデジタルディスラプションが起きていることなどがあります。
このような状況で、ローコード開発やノーコード開発の大きな利点である開発工数の削減や、開発者に高度なスキルを求めないこと点が、業務効率化・生産性向上に貢献するのではないか期待され、注目を浴びているのです。
【関連記事】
ローコード開発ツール・プラットフォーム17種を比較!おすすめのツールは?
3. ローコード開発とノーコード開発の違いは?
冒頭でもお伝えした通り、ローコード開発とノーコード開発の違いは、ローコード開発が開発におけるソースコードの記述を最小限に抑えながら、必要に応じてプログラミングも行う解発手法であるのに対し、ノーコード開発ではまったくソースコードを書かない点です。
ローコード開発、ノーコード開発それぞれのメリット・デメリットをご紹介いたします。
4. ローコード開発のメリット・デメリット
まずは、ローコード開発について、メリット・デメリットを見ていきましょう。
ローコード開発のメリット
ローコード開発の主なメリットは、「開発の時間・コスト削減」「高度な専門性がなくても開発できる」「柔軟な機能拡張ができる」の3点です。
開発の時間・コスト削減
もっとも大きなメリットとしては、「開発の時間・コスト削減」が挙げられます。
「ローコード開発、ノーコード開発とは?」でもお伝えしたように、ローコード開発では大部分をあらかじめ用意された機能単位を組み合わせてアプリケーション開発を行います。
この結果、必要最小限のプログラミングで開発を済ませられ、開発期間を大幅に削減できます。その分、人件費を中心とする開発コストも圧縮できる点がメリットです。
高度な専門性がなくても開発できる
ローコード開発は、ノーコード開発のようにまったくソースコードを書かないわけではないため、開発者にはある程度のプログラミングのスキルが必要です。
ただ、大部分はあらかじめ用意されている機能単位の組み合わせで開発できるため、本来、開発に必要だったはずの幅広くかつ高度な専門性は不要です。
用意された機能だけでは間に合わない部分のプログラミングで必要なスキルだけあれば良いため、後から付けるとしてもハードルが低くて済みます。
柔軟な機能拡張ができる
繰り返しになってしまいますが、ローコード開発では、ノーコード開発のようにまったくソースコードを書かないわけではありません。
そのため、希望に合わせて機能拡張やカスタマイズが可能です。
ローコード開発ツールに備わった機能を活用しつつ、足りないところはプログラミングで補えるため、スクラッチ開発とノーコード開発の良いところ取りが可能です。
ローコード開発のデメリット
一方、ローコード開発のデメリットといえるのは「誰にでも使えるわけではない」「ゼロからプログラミングするよりは自由度が低い」の2点です。
誰にでも使えるわけではない
「高度な専門性がなくても開発できる」でもお伝えしましたが、ローコード開発によるアプリケーション開発では、機能拡張や画面デザインなど、希望に沿ったカスタマイズが可能です。ただ、そのためには開発者にソースコードを記述するスキルが必要です。裏を返せば、プログラミングのスキルがまったくない人には開発が難しいということです。この点は、ローコード開発のデメリットであり、ノーコード開発に軍配が上がります。
ゼロからプログラミングするよりは自由度が低い
「柔軟な機能拡張ができる」でも触れたように、ローコード開発では、開発ツール(開発プラットフォーム)にない機能の追加などは、ソースコードの記述で実現できます。とはいえ、開発ツール(開発プラットフォーム)の仕様の範囲内となり、フルスクラッチで開発するのに比べれば自由度は下がります。
5. ノーコード開発のメリット・デメリット
では、ノーコード開発のメリット・デメリットは何でしょうか?
ノーコード開発のメリット
まずは、メリットから見ていきましょう。
ノーコード開発のメリットには、「開発の時間・コスト削減」「プログラミングの知識のない人でも使える」「現場のニーズに合わせてすばやくカスタマイズできる」の3つがあります。
開発の時間・コスト削減
ノーコード開発では、ソースコードをまったく書かずに機能単位を組み合わせるだけで開発が行えます。
これにより、通常なら数ヵ月単位で開発期間が必要であるところを、簡単なアプリケーションであれば、数分で開発することも可能です。
プログラミングの知識のない人でも使える
ノーコード開発ツール(プラットフォーム)は、わかりやすくビジュアル化されたユーザインタフェース(GUI))を使って機能単位を組み合わせたり用意された仕様を選択したりするだけで開発が行えるため、ソースコードの記述が不要です。
このため、プログラミングの知識がない人でもアプリケーション開発が可能です。
現場のニーズに合わせてすばやく変更できる
業務にアプリケーションを使用する中で、時間の経過とともに業務フローなどが変更になるケースも出てくるでしょう。それに合わせてアプリケーションも変更したいという場合、ソースコードの記述が必要だと、プログラミングの専門スキルを持つ人しか対応できません。場合によっては社外に外注する必要も出てくるでしょう。そうなれば、時間も金銭コストもかかってきます。
しかし、ソースコードの記述が不要なノーコード開発であれば、現場の担当者がすぐに対応できます。このため、アプリケーションの変更にかかるリードタイムを大幅に短縮することができます。併せて金銭コストも抑えられます。
ノーコード開発のデメリット
ノーコード開発にもメリットばかりではありません。
ノーコード開発のデメリットは、「できることが限られる」「大規模な開発には向かない」「ツール選定が難しい」の3点です。
できることが限られる
ノーコード開発では、開発ツール(プラットフォーム)に用意された機能の範囲でしか機能や仕様を実現することができません。
そのため、スクラッチ開発はもちろん、ローコード開発と比較すると自由度が低い場合が多いでしょう。
大規模な開発には向かない
利用する開発ツールによって異なりますが、ノーコード開発は自由度が低い場合があるため、基幹業務システムのような大規模なアプリケーション開発では、自社にマッチしたシステムを実現しづらいでしょう。このため、ノーコード開発は大規模な開発には向かない可能性があります。逆に向いているのは、特定の部門のみで利用したり、全社で使うとしても特定の業務に利用するためのアプリケーション開発です。
ツール選定が難しい
ノーコード開発ツール(プラットフォーム)には、無料で利用できるものから有料のものまでさまざまなものがリリースされており、それぞれに特徴があります。各ツールで、開発を想定されているアプリケーションもさまざまなので、自社の目的に合ったツールを選定する必要があります。このツール選定に工数がかかります。また、本当に自社に適した開発ツールを選ぶのは簡単なことではありません。この点もデメリットといえます。
6. ローコードとノーコードの比較表
ローコードとノーコードの比較をわかりやすく示した表が、次の通りです。
| ローコード | ノーコード | |
|---|---|---|
| 開発手法の特徴 | GUI(ドラッグ&ドロップ)を中心に、一部コード記述も可能 | GUI操作のみでアプリ構築可能、基本的にコード不要 |
| 対象ユーザー | 開発経験のあるエンジニア、IT部門、または多少技術スキルを持つ担当者 | 業務部門の担当者、非エンジニア、一般社員 |
| コーディング | 一部必要(複雑なロジックや画面のカスタマイズなど) | 原則不要(ドラッグ&ドロップなどの視覚的な操作) |
| 柔軟性・拡張性 | コーディング併用で柔軟なカスタマイズが可能 | 柔軟性は低め。提供される機能に制約あり |
| 開発スピード | ノーコードよりは遅いが、従来開発より大幅に速い | 非常に速い。短期間でアプリを立ち上げ可能 |
| 適用範囲 | 業務システム、Webアプリケーション、モバイルアプリなど、幅広いシステム開発 | 業務効率化ツール、簡易的なWebアプリ、データ分析ダッシュボードなど |
| 情報セキュリティ | 高い(ただし、開発者のスキルに依存する部分も) | プラットフォームに依存(一般的に高いセキュリティレベル) |
| 学習コスト | プログラミング知識があると効果的に活用できるが、完全初心者には少しハードルあり | 直感的操作が可能で初心者でも習得が容易 |
| 導入コスト | ツール費用に加え、ある程度の開発工数が発生 | 導入コストを最小限に抑えられる |
| 主な利用シーン | 既存システムとの連携が必要な場合、ある程度の拡張性を求める場合 | 業務担当者が自力で効率化ツールを作りたい場合、シンプルな業務改善 |
7. ローコード開発ツール、ノーコード開発ツールの導入フロー
ローコード開発ツールやノーコード開発ツールを導入する際のステップをご紹介いたします。
1.目的とニーズを明確化する
まずは開発するアプリケーションの目的と、それに必要な機能、開発体制、予算などを明確にしていく必要があります。
どのような課題を解決したいのか、たとえば、業務プロセスの自動化や顧客体験の向上、データ分析の効率化など具体的な目標を設定し、そのために必要な機能(データベース連携、外部APIとの連携、モバイル対応、オフライン機能など)を洗い出しましょう。
さらに、開発メンバーのプログラミングスキルやITリテラシーを考慮し、適切なツールを選択します。
開発予算については、ツールの利用料金だけでなく、開発工数や運用コストも考慮して予算に見合ったツールを選びましょう。
2.ツールの特徴・機能を比較する
ローコード開発ツールやノーコード開発ツールは、それぞれ提供している機能や得意分野が異なるため、導入前に比較検討を行うことが不可欠です。開発したいシステムに必要な機能がそろっているかを確認しましょう。
単に機能数の多さだけでなく「自社の利用目的に対して本当に必要な機能が備わっているか」「ユーザーがストレスなく操作できるか」という視点で比較することが、ツール選定を成功させる大きなポイントになります。
3.無料トライアルやデモを活用して検証する
多くのツールでは、無料トライアルやデモ環境が提供されています。実際にツールに触れてみることで、使い勝手や機能を体感し、自社のニーズに合致するかを判断できるため、無料トライアルやデモを活用して、導入候補のツールの絞り込みを行いましょう。
4.導入後の運用計画を立てる
ツールの導入後、円滑に運用していくために運用計画を立てておくことも重要です。
開発したアプリケーションの運用体制、情報セキュリティ対策、バージョンアップ対応などを検討しておきましょう。
8.ローコード開発ツール、ノーコード開発ツールの選び方・比較ポイント
ローコード・ノーコード開発ツールは種類が豊富で、提供される機能や得意分野も異なります。そのため、自社がどのような目的で導入するのかを明確にし、複数の観点から比較検討することが重要です。ここでは、具体的な選び方のポイントとして以下の7つを解説します。
開発対象
まず確認すべきは、対象となるアプリケーションの種類です。Webアプリ・モバイルアプリ・業務システムなど、ツールによって得意分野が分かれます。たとえば社内の業務効率化を目的とする場合は、データベース連携やワークフロー自動化が得意な開ツールが適しています。
一方、外部向けに提供するサービスやアプリを想定するなら、UIデザインの自由度が高いWeb・モバイル対応型のツールを選ぶとよいでしょう。自社が求める成果物に直結する開発対象をサポートしているかが、最初の重要な判断基準となります。
機能
次に注目すべきは、ツールが提供する機能の幅です。ドラッグ&ドロップでのUI構築は標準的ですが、それに加えてデータベース連携・API連携・外部サービスとの統合・バージョン管理・アクセス権限管理など、自社業務に必要な機能を備えているか確認しましょう。
機能の不足はあとからの追加コストにつながるため、導入前に必ず確認しておきましょう。
使いやすさ
ツールの使いやすさは、導入効果を左右する大きな要素です。非エンジニアでも直感的に操作できるインターフェースであるか、必要最低限の学習で使いこなせるかを見極める必要があります。
チームにエンジニアがいる場合は、多少学習コストがかかっても柔軟性の高いツールが選ばれやすい一方、業務部門主導で利用する場合は低学習コストで利用可能なノーコード寄りのツールが望ましいでしょう。また、日本語対応の有無やマニュアルのわかりやすさも、実運用における使いやすさに直結するポイントです。
拡張性・カスタマイズ性
ツールによっては、プラットフォーム内でできることが限られている場合があります。そのため、独自の機能追加やカスタマイズがどこまで可能かを確認することが重要です。
とくにローコードツールはコード記述により柔軟にカスタマイズできる点が強みであり、将来的な要件変更や新しい機能追加に対応しやすい傾向があります。一方、ノーコードツールは機能拡張の自由度は低いものの、テンプレートや外部連携機能が豊富なサービスを選べば、一定の柔軟性を確保できるでしょう。
情報セキュリティ
業務アプリケーションを扱う以上、セキュリティ対策は必須です。ツールが提供する情報セキュリティ対策や、国際的な認証の取得状況を確認する必要があります。
また、個人情報や機密データを扱う場合は、データ暗号化・権限管理・監査ログなどが十分に備わっているかが重要です。クラウド型ツールを利用する場合は、データセンターのセキュリティ基準やバックアップ体制についても事前に把握しておきましょう。
サポート体制
導入後の定着やトラブル対応には、ベンダーのサポート体制が大きく影響します。専任サポート窓口の有無や、導入支援サービス、教育プログラムの提供状況を確認しましょう。
社内にノウハウがない段階では、サポートが充実しているツールの方が定着しやすい傾向があります。
料金体系
最後に料金体系です。ツールによっては月額料金のほか、ユーザー数や開発したアプリケーション数に応じて課金される仕組みがあります。小規模な利用であればユーザー数課金型が適していますが、利用部門が拡大する可能性があるなら固定費型の方が長期的にコストを抑えられる場合もあるでしょう。
自社の予算や利用規模に合った料金体系を選ぶことで、長期的なコスト最適化につながります。
9. ローコード開発ツール、ノーコード開発ツールを導入する時の注意点
最後に、ローコード開発やノーコード開発を行うツール(プラットフォーム)を導入する際の注意点をご紹介いたします。
ローコード開発ツールにするか?ノーコード開発ツールにするか?
まず、自社に導入するローコード開発ツール、ノーコード開発ツールの選定作業があります。
ローコードにするか、それともノーコードにするかという段階から検討する必要があるため、あらかじめ自社の導入目的をできるだけ詳細に明らかにし、目的を達成できるツールを選定しましょう。
保守や運用体制を構築しておく
選定したツール、プラットフォームを導入した後は、社内で保守・運用していくことになります。その管理体制を整備しておく必要があります。ツールに関して社員から問い合わせがあった場合やベンダーなどとの連絡の必要があった際に誰が窓口となるのか、不具合が出た際はどのようなフローで対応するのかといったことを決めておきましょう。
無料のツールや海外製のツールの場合、どの程度のサポートを受けられるのかをチェックしておきましょう。
情報セキュリティ対策をチェックする
また、ツール、プラットフォームのセキュリティレベルについても確認しておく必要があるでしょう。
自社のセキュリティポリシーに合致していることは前提として、ツールそのもののセキュリティやベンダーの信頼性、いざインシデントが起きた際にどのような対応をしてもらえるのかまで確認しておきたいところです。
業務プロセス改善に関する知識が必要
ローコード開発ツールやノーコード開発ツールを導入し、アプリケーションを開発したら、それを業務効率化や生産性向上、DX推進などのために活用していくことになります。
より効果的にこれらを実現していくためには、業務プロセス改善に関する知識が必要です。
業務プロセス改善に関するスキルがまったくないという場合は、書籍やオンラインセミナーなどでも知識が得られるでしょう。
10. ローコード開発ツールのおすすめ10選
最後に、ローコード開発ツール、ノーコード開発ツールのおすすめ10選をご紹介いたします。
まずは、ローコード開発ツールから。
【関連記事】
ローコード開発ツール・プラットフォーム17種を比較!おすすめのツールは?
OutSystems(アウトシステムズ)
https://www.outsystems.com/ja-jp/
OutSystemsは、ポルトガル発のローコード開発プラットフォームで、OutSystems社(OutSystems, Inc.)が2001年から提供しています。日本法人であるOutSystemsジャパン株式会社が、2018年に設立されています。
OutSystemsを活用すれば、Webアプリケーションやモバイルのネイティブアプリケーションの開発が行えます。
OutSystemsは有料のツールですが、無償トライアルがあり無償トライアルでも全機能を体験できます。最大100ユーザーが登録できるので、チームでの開発でも利用可能です。
無償トライアルは、フォームに必要項目を入力してサインアップするだけで、1分でインストールでき、簡単なアプリなら5分以内に作成することもできるというスピーディさが特徴です。
Microsoft PowerApps(マイクロソフト・パワーアップス)
https://www.microsoft.com/ja-jp/power-platform/products/power-apps
Microsoft PowerAppsは、マイクロソフト社(Microsoft Corporation)が提供するローコード開発プラットフォーム「Power Platform」のサービスの一つで、クラウドサービスとして提供されています。
ビジネスアプリケーションを迅速に作成できるだけでなく、組織内での共有もスピーディかつ簡単に行えます。開発は、GUIとExcelのような関数を組み合わせて、ブラウザ上で行います。複数のテンプレートが用意されており、スピーディな開発が可能です。
Microsoft のDynamics 365やOffice 365のエンタープライズプランなどを契約していると、PowerAppsを無料で利用できます。そうでない場合は、1ユーザー当たり月額料金760円から単体契約も可能です。30日間の無料トライアルも用意されています。
Kintone(キントーン)
Kintoneは、サイボウズ株式会社が提供する、システム開発経験がないユーザーでも直観的にアプリケーションを簡単に作成できるクラウドサービスです。導入実績は2万社以上。
APIが豊富に用意されており、さまざまなシステムとの連携が可能で、この部分を利用する場合はローコード開発プラットフォームとして、連携せずに単体のアプリケーションを作成する場合はノーコード開発プラットフォームとして、活用できます。Javascriptによるカスタマイズも可能です。
初期費用は無料。ライトコース(月額780円/1ユーザー)、スタンダードコース(月額1,500円/1ユーザー)、ワイドコース(月額3,000円/1ユーザー)の3つのプランが用意されています。
※2024年秋より価格改定が予定されています。
Oracle APEX(オラクル・エーペックス)
Oracle APEXは、データベース管理システムで有名な米オラクル社(Oracle Corporation)が提供する、エンタープライズ向けのローコード開発ツールです。クラウド版とオンプレミス版が用意されています。
なお、APEXとはApplication Expressの略でエーペックスと読みます。
Oracle Databaseに搭載されており、Oracle DatabaseをベースにしたWebアプリケーション開発フレームワークで、データベース言語であるSQLをOracle Database用に独自に拡張したプログラミング言語「PL/SQL」で、これはSQLの知識があればすぐに使えます。
Oracle Databaseのユーザーであれば、追加ライセンスを購入することなく利用できます。単体契約の場合も、月額360ドルからとなっており、低コストで利用できます(クラウド版の場合)。無料プランも用意されています。
intra-mart(イントラマート)
intra-martは、NTTデータ イントラマートが提供する日本製ローコード開発ツールで、導入実績は1万社以上、ワークフロー市場でシェアNo.1を誇ります。
エンタープライズ企業向けのシステム開発が可能なローコード開発プラットフォームです。グローバルに対応しており、日本語、英語、中国語など多言語対応しているだけでなく、各国のタイムゾーンも利用可能です。
数百種類ものAPIコンポーネントが用意されており、AI、OCR、RPA、電子署名などのサービス・製品との組み合わせも可能で、ワークフローを高度に自動化することができます。
すぐに利用できる豊富な業務アプリケーションも魅力です。
WebPerformer(ウェブパフォーマー)
https://www.canon-its.co.jp/products/web_performer/
WebPerformerは、キヤノンITソリューションズが提供するローコード開発プラットフォームで、Webシステムを素早く開発することができます。
登録した内容が、すぐに設計書に反映されるため、設計書の作成工程をも短縮することが可能。さらには、テスト工程も自動化することができます。
導入社数は、累計1,000社以上。
ニアショア開発や、内製化支援サービスも用意されており、自社のみでのローコード開発に不安のある企業でも導入できるようになっています。
TALON(タロン)
TALONは、株式会社HOIPOIが提供する日本製のローコード開発プラットフォームです。導入実績は、300社超。
「ブロックシステム」を採用しており、学習コストに時間をかけなくても、複雑なシステムを作ることが可能です。
自社のみでの開発に不安がある企業向けには、毎月無償のハンズオンセミナーを実施しています。また、パートナー企業による開発サポートサービスも用意されています。
料金は、オンプレミス版が50万円から、クラウド版が4万円からとなっています。
1ヵ月間の無料試用版も提供されています。
Retool(リツール)
Retoolは、米リツール社(Retool, Inc.)が提供するローコード開発プラットフォームで、Webサービスを簡単に作れます。同社は、2017年に設立された、比較的、新しい企業ですが、革新的なプラットフォームは多くの企業から注目を集め、すでに急成長を遂げています。
REST APIやGraphQL APIと連携して、外部サービスのデータを利用できるほか、必要に応じてJavaScriptでカスタムコンポーネントやロジックを追加し、拡張できます。
料金は、「Team(月額10ドル/1ユーザー)」「Business(月額50ドル/1ユーザー)」「Enterprise(要見積もり)」となっており、無料で使えるFreeプランも用意されています。
Mendix(メンディックス)
https://www.sw.siemens.com/ja-JP/mendix-low-code-platform-digital-enterprise/
Mendixは、ドイツの電機メーカーであるシーメンス社(Siemens AG)が提供するローコード開発プラットフォームです。
アプリ開発は基本的にデータ構造と画面をロジックでビジュアルに関連付けるだけで行え、オフライン動作も可能な、あらゆるデバイスに対応するアプリ開発が可能です。
作成したアプリケーションは、ワンクリックで、さまざまなクラウド、オンプレミスに展開可能です。
日本代理店が複数あるため、そこから購入することで、日本語でのサポートが受けられます。
Salesforce Platform(セールスフォース・プラットフォーム)
https://www.salesforce.com/jp/products/platform/low-code/
Salesforce Platformは、米セールスフォース社(Salesforce, Inc.)が提供するローコード開発プラットフォームです。世界トップシェアを誇るSFA/CRMである「Salesforce」の開発プラットフォームで、ローコード/ノーコードでのアプリ開発が可能です。
ワークフローや承認プロセスを自動化するLightning Flow、独自のコンポーネントを作成できるLightning Web Componentsなど、ローコード開発を強力に支援するツール群を提供されています。
JavaScriptを使ったローコード開発はもちろん、ビルダーを使ったノーコード開発まで対応しています。
11. ノーコード開発ツールのおすすめ10選
つづいて、ノーコード開発プラットフォームのおすすめを10点、ご紹介いたします。
Bubble(バブル)
Bubbleは、米バブル・グループ社(Bubble Group, Inc.)が提供するノーコード開発プラットフォームで、Webアプリの開発が可能です。
データベース、ユーザー認証、API連携など、Webアプリケーションに必要な機能が豊富に用意されており、外部サービスとの連携も容易に行えます。
世界中に多くのユーザーがいるため、コミュニティが活発で、フォーラムやチュートリアルなど、学習資料が充実しており、これらを利用できる点がメリットです。
プランは「Starter(月額29ドル)」「Growth(月額119ドル)」「Team(月額349ドル)」「Enterprise(金額は要見積もり)」があり、無料で利用できるFreeプランも用意されています。
Glide(グライド)
Glideは、米グライド・アップス社(Glide Apps, Inc.)が提供するノーコード開発プラットフォームで、GoogleスプレッドシートやExcelなどのスプレッドシートと連携してアプリを開発できる手軽さで人気を集めています。
スプレッドシートに入力したデータがアプリに反映されるため、データ管理が容易に行えます。
その手軽さから、スタートアップ企業や中小企業、個人開発者を中心に広く利用されています。従来の開発手法と比較して、開発コストや開発期間を大幅に削減できるだけでなく、専門知識がない人でも実用的なアプリを開発できるのが大きな魅力です。
プランは、「Team(月額99ドル)」「Business(月額249ドル)」「Enterprise(月額499ドル)」
PigeonCloud(ピジョンクラウド)
PigeonCloudは、株式会社ロフタルが提供する日本製のノーコード開発プラットフォームで、データベースを作成できるツールです。
顧客管理や問い合わせ管理、在庫管理、申請業務、請求管理などに活用できるデータベースを作成可能です。
チャート機能やカレンダー機能、ワークフロー機能が標準搭載されています。
料金は「ユーザー数プラン(月額1,100円/1ユーザー)」「同時ログイン数プラン(月額2,200円/1ユーザー)」の2タイプが用意されています。30日間の無料トライアルも可能です。
Notion(ノーション)
Notionは、米ノーション・ラボ社(Notion Labs, Inc.)が提供するノーコード開発プラットフォームです。
ドキュメント作成、タスク管理、データベース、Wikiなど、様々な機能を一つのプラットフォームに統合したサービスです。従来、複数のツールに分かれていた情報を一元管理できる点が最大の特徴です。
マーケティング、セールス、人事など、様々な業務やシーンに合わせたテンプレートが豊富に用意されています。テンプレートを活用することで、Notionをすぐに使い始めることができます。
プランは「プラス(月額8ドル)」「ビジネス(月額15ドル)」「エンタープライズ(金額は要見積もり)」があり、無料で利用できるフリープランも用意されています。
サスケWorks(サスケ・サークス)
サスケWorksは、株式会社インターパークが提供する日本製のノーコード開発プラットフォームです。
サスケWorksを活用して、採用管理アプリやメルマガ管理アプリ、日報アプリ、経費精算アプリ、請求書管理アプリ、案件管理アプリ、社員名簿アプリ、見積もり作成アプリ、お問合わせ管理アプリ、顧客管理アプリなどを作成することが可能です。
サスケWorksを利用しているほかの企業に、作成したアプリを販売することもできます。
料金は、「Standard Plan(月額5,000円)」「Premium Plan(月額1万5,000円)」で、それぞれ、11IDが付属しています。どちらのプランにも、30日の無料トライアルが用意されています。
Airtable(エアテーブル)
Airtableは、米エアテーブル社(Airtable, Inc.)が提供するノーコード開発プラットフォームで、データベースを作成できます。
一見すると従来のスプレッドシートソフトに似ていますが、データベースとしての強力な機能と柔軟性を兼ね備えている点が最大の特徴です。ExcelやGoogleスプレッドシートと似たUIなので、表計算ツールを使い慣れているユーザーに向いています。
あらかじめ用意されたテンプレートを活用することで、プロジェクト管理、顧客管理、タスク管理など、様々な用途に合わせたデータベースを簡単に作成できます。
プランは「Team」「Business」「Enterprise Scale」と、無料で利用できる「Free」が用意されています。
Zapier(ザピアー)
Zapierは、米ザピアー社(Zapier, Inc.)が提供するノーコード開発プラットフォームで、異なるWebアプリケーションを連携させ、自動化するサービスです。
Zapierは、Google Workspace、Salesforce、Slack、Gmailなど、ビジネスでよく利用される3,000以上のWebサービスとの連携に対応しています。
たとえば、Webサイトから問い合わせがあった際に、自動的に顧客管理システムに登録したり担当者に通知を送信したりといった用途に活用できます。
プランは、「Professional(月額4,714円)」「Team(月額1万6,269円)」「Enterprise(金額は要見積もり)」があり、無料で利用できる「Free」も用意されています。
14日間の無料トライアルも利用可能です。Click(クリック)
Clickは、MikoSea株式会社が提供する日本製のノーコード開発プラットフォームで、スマホ用のアプリを作ることができます。プログラミングをしたことない人でも、iOS Androidのアプリを同時にたったの1日で完成させることが可能という簡単さです。
ユーザー認証、データベース管理、通知機能、サブスクリプション支払い機能など、20種類以上の機能から必要とする機能を組み込む事ができます。またAPIを用いて、外部のサービスと連携することでさらに拡張することも可能です。
プランは「Standard(月額4,400円)」「Pro(月額1万9,600円)」があり、無料で利用できるFreeプランも用意されています。
Adalo(アダロ)
Adaloは、米アダロ社(Adalo, Inc.)が提供するノーコード開発プラットフォームで、モバイル用のアプリ(Webアプリ、ネイティブアプリ)を作成することができます。同社の設立者が「誰でも簡単にアプリを開発できる世界」を目指してAdaloを開発しました。
ECサイト、チャットアプリ、SNSなど、様々な種類のアプリを開発するためのテンプレートが用意されており、コンポーネントをドラッグ&ドロップで配置していくだけでアプリの画面設計が可能です。
開発したアプリは、iOSやAndroidのアプリストアで公開することができます。
プランは「スターター(月額45ドル)」「プロフェッショナル(月額65ドル)」「チーム(月額200ドル)」「事業内容(月額250ドル)」があり、無料で利用できるプランも用意されています。
APPBOX(アップボックス)
https://iridge.jp/service/appbox/
APPBOXは、株式会社アイリッジが提供する日本製のノーコード開発プラットフォームで、顧客向けにサービスを提供するための自社オリジナルアプリを開発できます。
導入実績は、300アプリ以上、8,906万ユーザー(2024年3月末時点)。
イチからオリジナルアプリを作成するだけでなく、既存のアプリに新機能を組み込み、バージョンアップすることも可能です。
料金は、初期費用25万円から、月額料金10万円から。
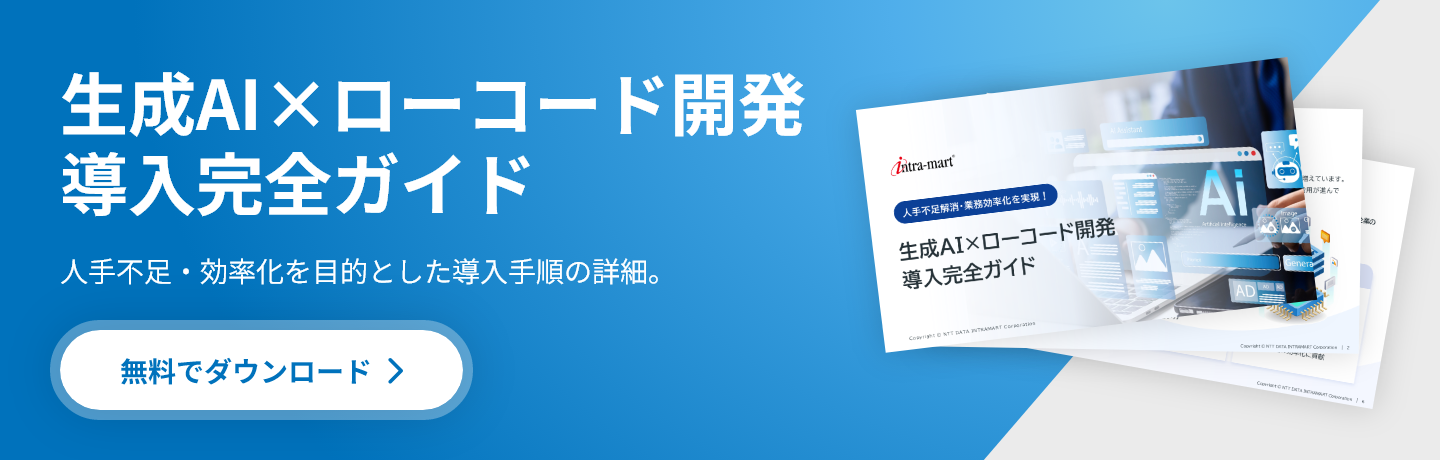
12. まとめ
ローコード開発、ノーコード開発について、メリット・デメリットやツールを導入する際の注意点などをご紹介しました。
今後、労働人口が減少する中、さらなるデジタル化が求められることが予測されます。
ローコード開発ツールやローコード開発ツールを活用して、省力で現場の細かいニーズにあったアプリケーションを短期間に開発できることは企業の競争力にも結びつくでしょう。
未導入の企業様も、この機会に情報収集や導入検討を始めてみてはいかがでしょうか。
Concept Book
ローコード開発・業務プロセスのデジタル化で豊富な実績を持つintra-martが、お客様のビジネスにどのような効果をもたらすのか、特長や導入効果など製品コンセプトを詳しくご紹介しています。

お困りごとがありましたら、お気軽にご相談頂ければと思います。
















