BPRとは? ~業務改善との違いからメリット・デメリット、成功事例までわかりやすく解説~
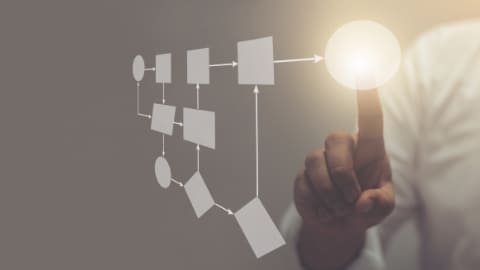
BPRとは、Business Process Re-engineering(ビジネスプロセス・リエンジニアリング)の頭文字を取ったもので、日本語では「業務改革」と訳されます。プロセスの観点から全社的に業務のフローや、情報システム、組織や職務などを見直して、再構築することをいいます。
BPRを実施することで、コスト削減や生産性向上などのメリットを得られます。
また、少子高齢化が進み、今後、労働人口が減少していく日本において、各企業がBPRに取り組むことで、日本全体の生産性を底上げすることにもつながります。
本コラムでは、BPRの概要やメリット、デメリット、実際に取り組む際のステップや成功事例をご紹介いたします。
【関連記事】
・BPMツールとは?業務改善に効果を発揮するBPMツールを比較
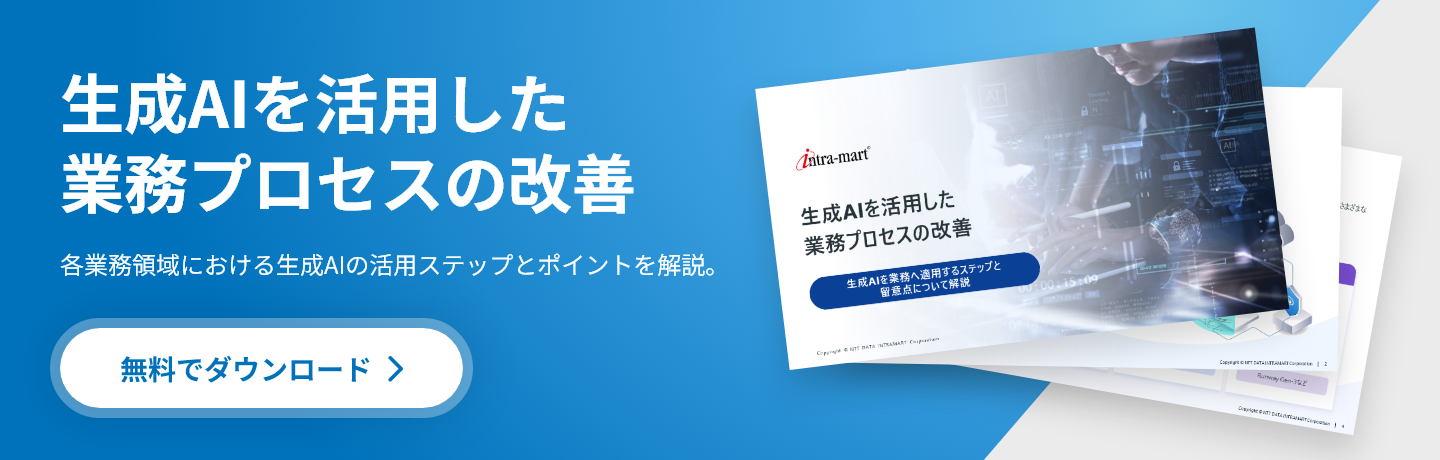
BPRとは
Business Process Re-engineering(ビジネスプロセス・リエンジニアリング)の頭文字を取ったもので、「ビーピーアール」と読み、日本語では「業務改革」と訳されます。
全社的な業務を、プロセスの観点から見直し、抜本的に変化させ、再構築することをいいます。
見直しの対象となるのは、業務フローや情報システム、組織、職務、管理機構などです。
80年代の後半に生まれ、マサチューセッツ工科大学の教授だったマイケル・ハマー(Michael Hammer)と、経営コンサルタントのジェイムス・チャンピー(James A. Champy)が1993年に出版した「Reengineering the Corporation: A Manifesto for Business Revolution(リエンジニアリング革命)」のベストセラー化によって広まったといわれています。
BPRの目的
BPRは、「業務効率化」「生産性向上」「コスト削減」「従業員満足度の向上」などを目的として実施されます。
業務効率化
全社的に業務プロセスを見直すことで、それまで存在していたムリ・ムラ・ムダを発見できます。これらを排除することで、業務効率化の実現につながります。
生産性向上
業務効率化は生産性向上の要素の一つであるため、業務効率化を実現することで、生産性向上にもつながります。ムリ・ムラ・ムダを排除した分、経営資源をもっと重要な業務に集中させることができます。
コスト削減
業務上のムリ・ムラ・ムダを排除できると、人件費や材料費、保管費など、さまざまなコストの削減につながります。
従業員満足度の向上
業務上のムリ・ムラ・ムダを排除することで、従業員にかかる負担を軽減できます。
また、より意義のある業務に集中できるようになってモチベーションアップにつながったりするため、従業員満足度の向上も期待できます。
BPRと業務改善の違い
BPRの定義を見ると、「業務改善」と非常に似ています。BPRの日本語訳が「業務改革」なので、両者の違いは「改革」と「改善」の違いであるといえそうです。
改革とは、方針なども含めて従来の制度などを改め、より良いものに変えることです。
一方、改善とは、現状をベースに最善の方向へ変化させていくことです。
つまり、BPRが全社規模での抜本的な変化であるのに対し、業務改善は一部の部署のみでの変化を指します。言い換えれば、業務改善はBPRの構成要素の一つであるともいえます。
BPRが注目される背景
「BPRとは」でもお伝えしたように、BPRの概念は1980年代から存在していました。日本で最初にBPRが注目されたのは、1991年から1993年にかけてのバブル崩壊でした。
1990年代は、BPRを導入して経営を立て直す企業が多かったようです。
それが、近年、BPRに継続的に取り組むことを支援するITツールであるBPMの市場が世界的にも拡大しており、日本でも1,000億円規模にまで成長しています。
ここまでBPRが注目されている背景は何でしょうか?
今また注目を浴びるようになっている背景には、日本における少子高齢化があります。少子高齢化による労働人口の減少をカバーするため、政府は働き方改革を推進してきました。企業側としても、BPRに取り組むことで、希少な労働人口を効率よく活用する必要があります。そこで、BPRが再び注目されるようになったのです。
BPRのメリット・デメリット
BPRに取り組むことで、「BPRの目的」で取り上げたようなメリットの享受が期待できますが、一方でデメリットもあります。ここで、まとめてご紹介いたします。
BPRのメリット
BPRに取り組むメリットは、「BPRの目的」で挙げた「業務効率化」「生産性向上」「コスト削減」「従業員満足度の向上」を実現できることです。
これに加え、以下の3点のメリットも期待できます。
業務全体を把握できる
BPRに取り組む過程で、社内の全業務が可視化されます。
これは、BPRのステップの一つでもありますが、BPRに取り組まなければ、なかなか全社的に業務を可視化・把握する機会はありません。
業務全体を把握することは、BPRの実現だけでなく、さまざまな経営判断の材料にもなります。
従業員の意識改革につながる
BPRに取り組む過程では、ヒアリングを行うなど、従業員に巻き込んでいくことになります。こうして従業員一人ひとりがBPRに参加することにより、業務に対する意識が高まり、BPRを継続しやすい土壌が整います。
経営判断のスピード向上
目まぐるしくビジネス環境が変化する現代において、経営判断のスピード向上は競争力に直結します。
BPR取り組む中で、経営判断のスピードを低下させている原因も見えてきます。これを解消することで、経営判断のスピード向上が可能です。
BPRのデメリット
一方、BPRを実施するデメリットといえるのが、次の2点です。
工数・時間がかかる
BPRの対象範囲は全社となるため、工数・時間がかかります。実施するとなれば、投入する人員や費用、時間は大がかりなものになります。
しかも、基本的に、全社のプロセスすべてを再構築するまで、途中でやめることもできません。
従業員との間に軋轢が生じる恐れがある
BPRを実施する中で、現状の業務や組織が大きく変わる可能性が高いです。しかし、人は変化を嫌うもの。改革に対して反発を覚える従業員も少なからずいるでしょう。
これを回避するため、取り組みの開始前に、従業員に対してBPRの重要性や目的について丁寧に説明し、理解と賛同を得ておく必要があります。
BPRを進めるプロセス
三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社がまとめた総務省の資料「民間企業等における効率化方策等(業務改革(BPR))の 国の行政組織への導入に関する調査研究(平成22年3月)」では、「BPR実施の一般的ステップ」としては、以下の5段階・8ステップが紹介されています。
なお、特に重視したいのは(1)、(3)、(4)だといいます。
ステップ1:検討
(1)目的・目標の設定
BPRを実施する目的を明確にし、目的に則って目標を設定します。
さらに、これを全社に周知しましょう。従業員一人ひとりの理解と協力を仰ぐためには、ただ告知するだけでなく、質疑応答を含む説明会などを開催するなど、丁寧に落とし込んでいく必要があります。
(2)対象とする業務範囲の設定
基本的にはBPRの対象範囲は全社のすべての業務です。
これらを具体的かつ明確に把握するために、業務範囲を設定しましょう。
また、部分的にスタートする場合は、優先度の高い業務から実施すべきでしょう。
その対象業務をこのフェーズで明確にしておきます。
ステップ2:分析
(3)分析・課題の把握(業務内容、フロー、組織)
ステップ1で明確にした目的や目標を踏まえ、対象業務の従事者に対してヒアリングを実施し、ABC分析、プロセスマッピング、ベンチマーキング、BSC(バランススコアカード)などの手法を用いて、現状の分析を行います。
分析結果から、現在の業務に横たわる課題を明らかにしましょう。
ステップ3:設計
(4)戦略・方針の策定、実施方法の検討
ステップ2で得た分析結果を元に、ステップ1で設定した目標に沿って、戦略・方針を策定します。
戦略・方針が決まったら、具体的な変革、つまり、業務の代替手段や、変更後の組織・職務などを検討していきましょう。
(5)ビジネス・プロセスの設計(業務フロー、ルール、組織)
具体的な実施方法が定まってきたら、変革後のビジネス・プロセスを設計していきます。
このフェーズを効率化してくれるのがBPMツールと呼ばれるものです。BPMツールとは、BPM(Business Process Management/ビジネスプロセス管理)を実行するソフトウェアのことです。BPMツールを活用することで、BPMを可視化し、効率化することができます。
BPMツールについて詳しくは、下記の記事もご覧ください。
【関連記事】
BPMツールとは?業務改善に効果を発揮するBPMツールを比較
ステップ4:実施
(6)変更の実施
ステップ1~3までに整えてきた準備を元に、変革を実施します。 BPRのプロジェクトリーダーは、全体の進捗状況を把握・管理してください。 ステップ1で明確にした目的・目標からブレないよう、適宜、立ち返りながら実施しましょう。
ステップ5:モニタリング・評価
(7)業務モニタリング
変革を実行したら、新しいプロセスでの業務について評価するために、モニタリングを行います。
現場の担当者に対して、各業務にかかっている工数・時間、ミスの発生数・率などの具体的な数値をヒアリングしましょう。
(8)効果測定・達成度評価
業務モニタリングで得た数値と、目標値を比較して、効果測定・達成度評価を行います。 また、改善につなげるため、数値以外の定性的な評価も行いましょう。この時も、現場の担当者へのヒアリング内容が元となります。
BPRを進める主な手法
BPRを進める主な手法は、以下の2つです。
・ERPを導入する
・BPOを活用する
それぞれの手法について詳しくチェックしておきましょう。
ERPを導入する
BPR の中で、情報システムや経営上の意思決定の見直し、再構築する際におすすめしたいのがERPです。
ERPとは、Enterprise Resource Planningの頭文字を取ったもので、日本語では「企業資源計画」と呼ばれ、経営資源であるヒト・モノ・カネ・情報を有効活用するという考え方や、これを実現するためのシステムを指します。
ERPによって、社内のさまざまな部門や担当者でバラバラに管理されていた情報を集め、一元管理することで、業務効率化につながるだけでなく、スピーディーな経営判断をより高い精度で下せるようになります。
BPOを活用する
BPR を行う中で、業務をスリム化したい場合に活用できるのがBPOです。
BPOとは、Business Process Outsourcingの頭文字を取ったもので、簡単にいえば業務を社外へ委託することです。
要な業務でありながら、社内で実施することで非効率化を招いている場合や、従業員にかかる負担が大きいことがわかった場合、人権費を増やせない時などは、BPOを利用しましょう。
BPRを成功させるためのポイント
BPRを成功させるためのポイントは、主に以下の6点です。
・組織へ必要性や方針を浸透させる
・課題や目標を明確にする
・一から作り直すつもりで設計する
・スモールスタートを意識する
・BPRの対象業務を設定する
・PDCAサイクルを回す
各ポイントを確認して自社での取り組みに活かしてみてください。
組織へ必要性や方針を浸透させる
BPRは、既存の業務プロセスを根本から見直し、新たな価値を生み出すための大規模な改革です。そのため、改革の効果を最大化するには、まず「なぜBPRに取り組むのか」という目的や背景を、組織全体で共有することが重要だといえます。
とくに、現場レベルの従業員にとっては、BPRは「業務のやり方が変わる」「新しいシステムに対応しなければならない」といった不安や抵抗感を生む要因になり得ます。そうした不安を払拭するためにも、経営層はBPRの必要性を明確な言葉で説明し、組織全体にビジョンを提示することが必要です。
このとき、トップダウンだけでなく、ボトムアップのアプローチも組み合わせることが有効です。現場の意見を吸い上げ、改革の方向性に反映させることで、従業員の納得感と当事者意識が高まります。
最終的には、BPRが「経営戦略の一環として必要不可欠な取り組みである」という共通認識を社内に浸透させることが成功のための基礎となるでしょう。
課題や目標を明確にする
BPRを推進する際には、漠然とした理想像ではなく、現実の課題を正確に把握し、それに対する明確な目標を設定することが不可欠です。具体的な問題が特定されていないままでは、改善の対象も定まらず、結果として現場の混乱や工数の無駄を招いてしまいます。
まずは、現状の業務プロセスを可視化し、業務フロー図やプロセスマップを作成しましょう。そのうえで、各プロセスの所要時間や工数、エラーの発生頻度などを数値的に洗い出し、どこにボトルネックがあるのか、何が非効率なのかを分析します。
その後、改善したい課題に対して「どのような状態を目指すのか」という目標を設定します。たとえば、「見積作成時間を30%短縮する」「申請・承認プロセスを2営業日以内に完了させる」「エラー発生率を半減させる」など、具体的で測定可能なKPIを定めることが望ましいでしょう。
また、こうした課題と目標の整理には、現場の意見や顧客からのフィードバックも重要な情報源となります。業務に携わる従業員が感じている非効率や改善ニーズは、経営層が気づきにくい重要なポイントです。ボトムアップのヒアリングを通じて、実態に即した課題設定を行うことが、BPR成功の重要なポイントだといえます。
一から作り直すつもりで設計する
BPRの最大の特徴は、「既存の業務を前提にしない」ことにあります。つまり、今ある業務の延長線上で改善を図るのではなく、ゼロベースで設計し直すことで、大幅な効率化や価値創出を実現することが目的です。
したがって、業務の再設計にあたっては、「この業務は本当に必要なのか」「このフローは最短・最適なのか」といった根本的な問いを投げかけながら進める必要があります。過去の慣習や既存のシステムにとらわれず、理想的な業務像を描く姿勢が求められるでしょう。
この段階では、業務プロセスの流れだけでなく、組織構造や役割分担、使っているツールや情報の流れ、さらには顧客との接点までを総合的に見直すことが重要です。必要に応じて、業務の統合・分割や担当の変更、アウトソーシングの活用なども視野に入れましょう。
また、設計段階では現場の声を積極的に取り入れることも大切です。理論的には理想的なプロセスであっても、現場での運用に適していなければ形骸化してしまう恐れがあります。従業員の理解と協力を得ながら、「使いやすく、効果が実感できる」業務プロセスを構築することが、真に有効な再設計といえるでしょう。
スモールスタートを意識する
BPRは変化の規模が大きいだけに、全社一斉に改革を進めようとすると失敗リスクも大きくなります。そのため、はじめは影響範囲を絞った「スモールスタート」を意識することが、成功への近道です。
たとえば、特定の部門や業務フロー、単一の業務ツールなど、限定的な範囲で改革を試行し、改善効果を可視化してから横展開する方法が有効です。これにより、リスクを最小限に抑えながら、早期に成功体験を生み出すことができます。
スモールスタートには、現場の協力を得やすくなるという副次的効果もあります。BPRは現場にとっては負担を伴う場合があるため、成功事例を通じて「変えてよかった」という実感を持ってもらうことが、全社的な推進の原動力となるでしょう。
また、小規模な改革から得られた知見は、他部門への展開時の重要な参考材料になります。プロジェクトマネジメントの観点でも、実施手順や人員体制、課題発生時の対応フローなどが明確になるため、スムーズな拡大が可能です。
このように、BPRを段階的に進めることで、失敗リスクを減らしながら確実に成果を積み上げていくことができます。
BPRの対象業務を設定する
BPRは企業活動全体に影響を及ぼす大規模な改革であるため、最初からすべての業務を一斉に見直すのではなく、効果が見込める業務から段階的に進めるのが現実的です。そのためにはまず、どの業務をBPRの対象とするかを明確に設定しましょう。
たとえば、営業プロセスにおける見積・契約業務、人事部門での申請・承認フロー、購買部門の発注管理などは、比較的多くの企業でBPRの対象として選ばれやすい領域です。これらは定型化されている一方で、手続きが煩雑だったり、属人化していたりする傾向があるため、改善効果が見えやすく、社内の理解も得やすいのが特徴です。
また、業務全体をプロセスマップで可視化したうえで、プロセスごとのコスト・時間・エラー率などを分析することで、定量的に改善効果が見込める業務を優先的に選ぶことも有効です。
BPRの対象業務を明確に絞ることで、限られたリソースで最大限の効果を得ることができます。改革のスピードと質を両立させるうえで、対象業務の選定は非常に重要です。
PDCAサイクルを回す
BPRは一度設計して終わりではありません。ビジネス環境や顧客ニーズ、内部の業務状況は常に変化し続けるため、継続的に業務プロセスを改善していく体制が必要です。そのために有効なのが、PDCAサイクルの活用です。
まずは「Plan(計画)」として、業務改善の目的やKPIを設定し、具体的なアクションプランを策定します。「Do(実行)」では、そのプランに基づいてプロセス改善を実施し、「Check(評価)」で効果を測定・分析します。最後に「Act(改善)」として、課題点を洗い出し、次のサイクルに活かしていきます。
このPDCAを単なる形式で終わらせず、定期的なレビューや改善会議を通じて運用に落とし込むことが重要です。現場のフィードバックを反映しながら、柔軟に軌道修正を行うことで、改革の成果を持続的に維持することができます。
また、改善の過程で得られたデータやノウハウを蓄積・共有することも欠かせません。部署をまたぐ横断的な情報連携やナレッジ管理体制を構築すれば、組織全体での生産性向上につながります。
BPRにおける真の成功とは、業務プロセスの継続的な進化を組織文化として根付かせることです。PDCAを軸とした改善活動の定着こそが、企業全体の変革力を高める重要なポイントだといえるでしょう。
BPRの成功事例
最後に、BPRの成功事例をご紹介いたします。
シックス・シグマの導入により年間で数千億円のコストを削減(製造業A社)
「民間企業等における効率化方策等(業務改革(BPR))の 国の行政組織への導入に関する調査研究(平成22年3月)」で紹介されているBPRの成功事例の一つが製造業A社の事例です。
製造業のA社は、シックス・シグマの導入により、年間で数千億円のコスト削減を実現しました。
シックス・シグマとは、米モトローラ社が開発した経営手法で、製造において100万回作業を行った際のエラーの発生を3~4回に抑えることです。ここから、製品やサービスの品質を一定以上に保つことで、顧客満足度を向上させる経営手法を指す言葉として定着しています。
A社では、米国大学と共同でシックス・シグマを応用して新商品開発などを行う手法を開発。また、10年という月日をかけてシックス・シグマの全社的な教育を実施しました。ただし、A社の従業員数が多いため、未だ半数しか教育が終わっていないといいます。
さらに、各事業部において、シックス・シグマのフレームワークと、前述の開発手法を適用するプロジェクトを実施しました。
こうした取り組みにより、A社では、年間で数千億円のコスト削減に成功したそうです。
全業務を可視化・定量化で、実証実験の無駄を削減(札幌市)
総務省の資料「地方公共団体における行政改革の取組(令和2年3月27日発表)」によれば、北海道札幌市は、労働力不足という課題に対し、生産性向上に向けたBPRを実施しました。
札幌市では、全業務のプロセスをタスクレベルに分解した上で、各タスクの業務量(概算時間)を集計。これにより、業務を可視化・定量化しました。これにより、業務効率化やDXのためのICT導入において、無駄な実証実験を削減できたといいます。たとえば、保育園の登降園管理システム導入における予想削減率は80%にもなったとそうです。また、ノンコア業務のBPO化にもつながりつつあるます。
さらに、政令指定都市同士である神戸市と連携協定を結び、マニュアルやフローなどを共有・突合。これにより、就学援助業務では一次審査の除外などでプロセスを効率化したり、審査を自動化して様式をOCRに最適化したりなどの業務効率化を実現しました。
なお、BPRにおいては民間企業と連携し、各種調査やデータクレンジング、プロセス整理などを依頼。庁内業務のフロー図も作成してもらったといいます。
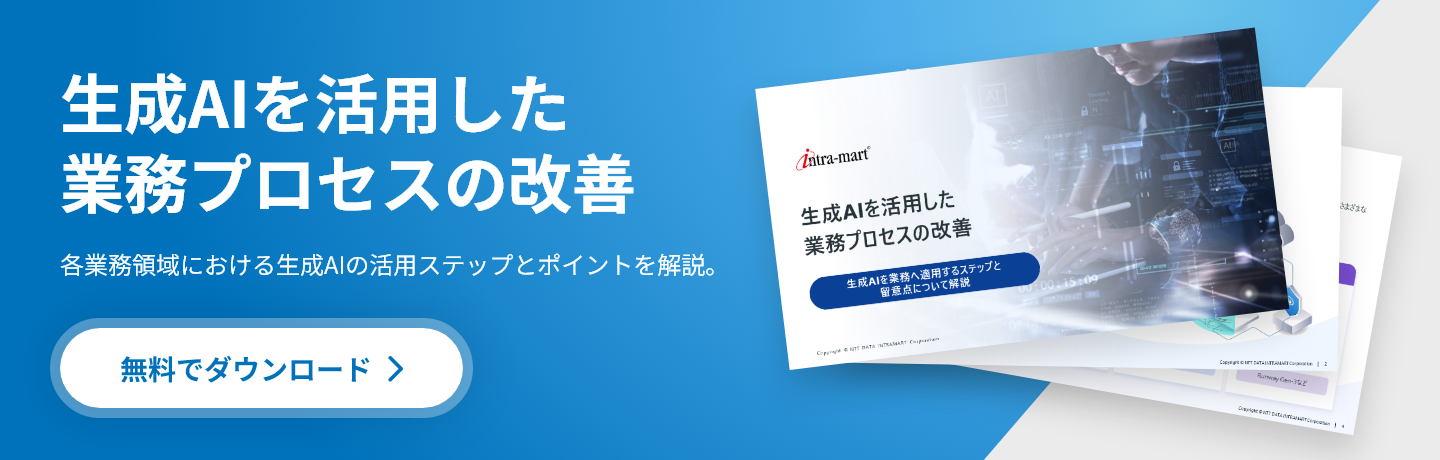
まとめ
BPRは、全社的な業務プロセスを見直し、再構築するもので、業務改善に比べると規模が大きく、かかる手間も期間も大きなものになります。
その分、実施する際の人的リソースと金銭的コストはかかりますが、成功すれば、得られるメリットも大きなものがあります。
実施の際には、ERPやBPMツール、BPOなどをうまく活用しながら、継続的な改善が行える体制を整えましょう。
なお、エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマートでもBPMツールを提供しております。
営業・販売、生産、物流など、システムの個別導入によって分断されたさまざまな業務を一連のプロセスとして可視化することが可能です。
詳しくは、こちらのページをご覧ください。
Concept Book
ローコード開発・業務プロセスのデジタル化で豊富な実績を持つintra-martが、お客様のビジネスにどのような効果をもたらすのか、特長や導入効果など製品コンセプトを詳しくご紹介しています。

お困りごとがありましたら、お気軽にご相談頂ければと思います。
















