サイロ化とは ~メリットやデメリットとシステムのサイロ化に対する改善方法まで解説

サイロ化とは、企業などの組織が業務に使用するシステムにおいて、部門や組織をまたいだシステム連携が行えないために、情報共有が行えない状態を指します。
情報システムにおけるサイロ化を放置すれば、データ連携が取れず、DXが進まなかったり、データ活用が限定的になって本来の価値を発揮できなかったりといったデメリットが生じます。
本コラムでは、サイロ化の概要とデメリット、解消することで得られるメリットや、具体的な改善方法をご紹介いたします。
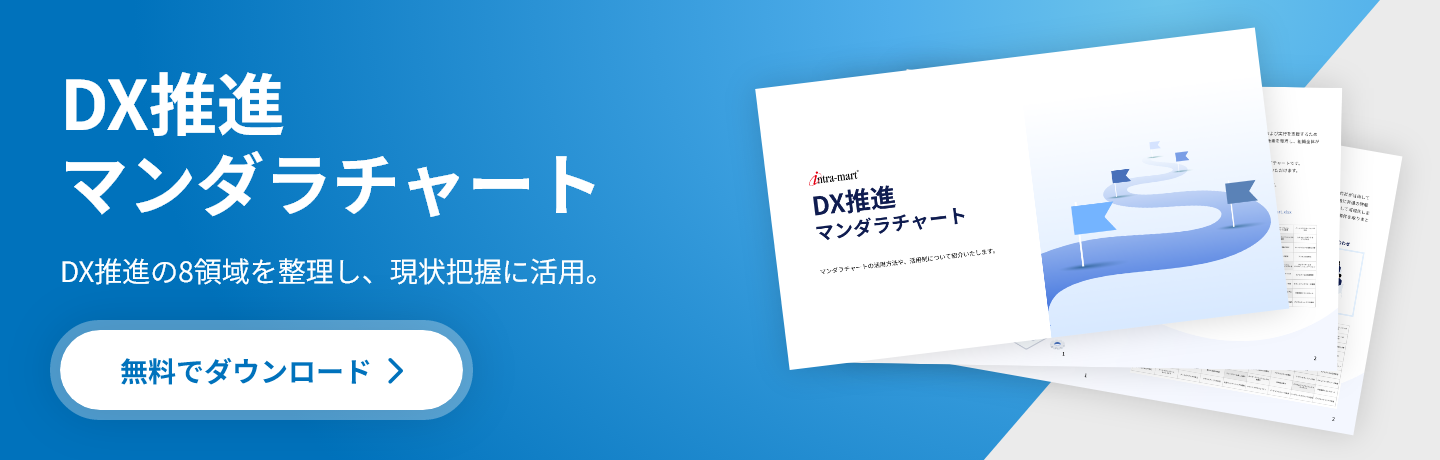
1. そもそもサイロ化とは
サイロ化とは、企業などの組織が業務に使用するシステムにおいて、部門や組織をまたいだシステム連携が行えないために、情報共有が行えない状態をいいます。
サイロとは?
サイロ化を理解する上で知っておきたいのが、元の「サイロ」の意味です。
サイロ(silo)とは、冬の間、米、とうもろこしなどの農産物や、家畜の飼料となる青草などを、生に近い状態で貯蔵しておく倉庫のこと。
各サイロは独立しており、貯蔵してある農産物が混ざらないように壁で隔てられています。
ここから転じて、組織ごとに独立して連携が取れない状態のシステムを指して「サイロ化」と呼ばれるようになりました。
なお、組織そのものが縦割り構造になっており、部門間で連携が取れない状態を「組織のサイロ化」と呼び、上記のようなシステムのサイロ化は「情報のサイロ化」と呼ばれます。
情報のサイロ化は、元をたどると組織のサイロ化が生み出したともいえます。
2. サイロ化のデメリット
情報システムのサイロ化は、DXやモダナイゼーションを推進する上で障害となります。
サイロ化には、ほかにも以下のようなデメリットがあります。
業務効率が悪化する
たとえば、顧客データや商品データなど、どの企業においても複数の部門で使用するようなデータがあるはずです。しかし、情報がサイロ化したままだと、各部門でそれぞれのシステムに入力しなければなりません。
それでは入力の手間がかかりますし、その分、ミスも起きやすくなります。また、データの管理が各部門に任されることになるため、最新に更新されないままのデータを使用してしまう部門が出てくる恐れもあります。
このように、情報がサイロ化していると、業務効率が良くありません。
さらに、それぞれの情報システムに個別のセキュリティ対策が施されたり、運用や保守が各部門で行われたりと、情報システムにかかる金銭コストにも無駄が生じます。
ビッグデータの活用ができない
社内には、顧客データや生産データ、技術データなど、創業時からの膨大なデータが蓄積されています。これらは貴重な経営資源であり、活用することで競争力強化につながりますが、活用しなければ宝の持ち腐れです。
情報がサイロ化していると、各部門でデータが分断した状態となり、全社的なデータ活用は行えません。各部門内でのデータ活用では、効果も限定的なものになってしまいます。
新たなデジタルテクノロジーを導入できない(DXが進まない)
各部門では、それぞれシステムの更改に対する考え方や方針も異なるため、積極的にモダナイゼーションしていく部門もあれば、いつまでも古いシステムを維持している部門もあるでしょう。
既存システムが古ければ、最新のデジタルテクノロジーを導入しようにも、データの構造やアーキテクチャなどが異なり、既存システムから新たなデジタルテクノロジーへのデータ連携が取れないことがあります。このため、新たなデジタルテクノロジーの導入を阻害します。
また、各部門で異なるシステムを利用していれば、全社的に統一のデジタルテクノロジーを導入する際の対応ハードルは上がります。
こうした理由から、サイロ化は経営層がリーダーシップを取り、全社一丸となって取り組む必要のあるDXを妨げるといえます。
3. サイロ化を解消するメリット
サイロ化を解消することで、上記のようなデメリットが改善され、次のようなメリットを得ることができます。
企業データの価値を高められる
サイロ化を解消できれば、各部門で分断されていたデータを統合した上で活用することができるようになります。
統合されたビッグデータをAIやBIツールで解析すれば、それまで実現できなかったような需要予測が可能になったり、新たな示唆を得られイノベーションにつながったりして、経営に役立てられるでしょう。
サイロ化を解消することで、既存の企業データの価値は高まるといえます。
DXを推進できる
「新たなデジタルテクノロジーを導入できない(DXが進まない)」でご紹介したことを裏返すと、サイロ化を解消すればDXが推進しやすくなるということになります。
既存のサイロ化したシステムを刷新して、全社統一のシステムを実現できれば、新たなデジタルテクノロジーとの親和性も向上し、導入・活用がしやすくなります。
データも全社で一元管理できるようになるため、活用もスムーズになり、DXの実現に近づきます。
4. システムのサイロ化に対する改善方法
では、システムのサイロ化を解消するためには、具体的にどのような方法があるのでしょうか?
ハード面での改善と、ソフト面での改善があります。
【ハード面での改善】データを統合するためのツールを導入する
ハード面での改善方法としては、社内でバラバラに管理されているデータを統合するために、デジタルツールを導入することです。
サイロ化して、データの構造やアーキテクチャがバラバラなデータベースを、統合できるソフトウェアが提供されているため、これを活用しましょう。たとえば、クラウド上で提供されているデータウェアハウス(DWH)などがあります。異なるシステムからのデータが、比較的短い期間で均質化されて統合されるため、サイロ化の解消に向いています。
【ソフト面での改善】部門間で連携する風土を醸成する
いくらハード面でのデータ統合に成功しても、データを管理運用する組織が縦割りのままでは、いつまた組織のサイロ化が起きてデータを部門内で抱え込む事態に陥るかわかりません。 組織の気風そのものを変革し、風通しを良くしていく必要があるでしょう。
具体的な方法としては、プロジェクトごとに各部門からメンバーを集めて協働させ、組織を横割りにする機会を増やしたり、ジョブローテーション制度を導入したりするほか、仕事以外にも社内イベントなど他部門のメンバー同士でコミュニケーションを取る機会を設けるなどがあります。
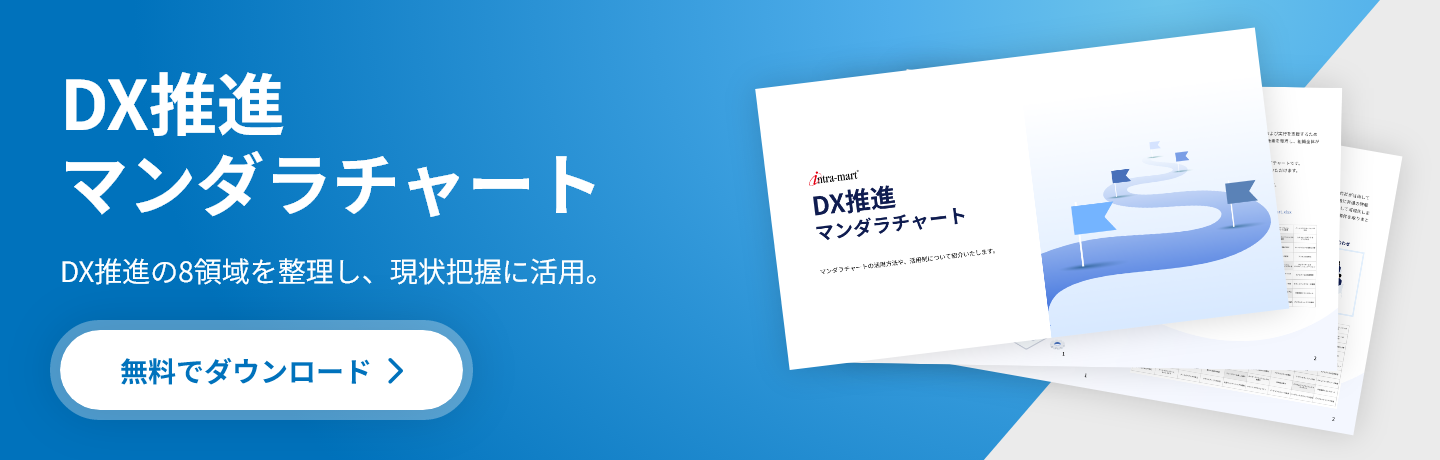
5. まとめ
情報システムにおけるサイロ化とは、部門や組織をまたいだシステム連携が行えず、情報共有が行えない状態をいいます。
サイロ化によって、業務効率が悪化したり、全社的なデータ連携が行えずDXが進まなかったりといった弊害が起きます。
解消のためには、サイロ化した情報システムからデータを均質化・統合できるデータウェアハウスなどのツール活用が有用です。
情報システムのサイロ化は、組織のサイロ化から生まれます。サイロ化を防ぐためにも、組織そのものの風通しを良くし、日頃から部門間でコミュニケーションを取りやすい風土を醸成する必要があるでしょう。
Concept Book
ローコード開発・業務プロセスのデジタル化で豊富な実績を持つintra-martが、お客様のビジネスにどのような効果をもたらすのか、特長や導入効果など製品コンセプトを詳しくご紹介しています。

お困りごとがありましたら、お気軽にご相談頂ければと思います。
















