デザインスプリントとは?~デザイン思考との違いから実行のプロセス、注意点まで解説~

デザインスプリント(The Design Sprint)とは、5日間(40時間)でアイデアからプロトタイプの完成までを完了する、課題解決のためのメソッドで、新たなサービスの創出などに活用されます。
米Google社のベンチャーキャピタル部門として設立された、当時のGoogle Ventures社(現在は「GV」に社名変更)が、2015年にスタートアップ企業に向けに提唱した手法です。
5日間という短い期間でプロセスを回すことで、スピーディにアイデアの価値を検証することができるため、ビジネス環境の変化が激しい現代に有効な手法といえます。
本コラムでは、デザインスプリントの実行プロセスや活用メリット、注意点などをご紹介いたします。
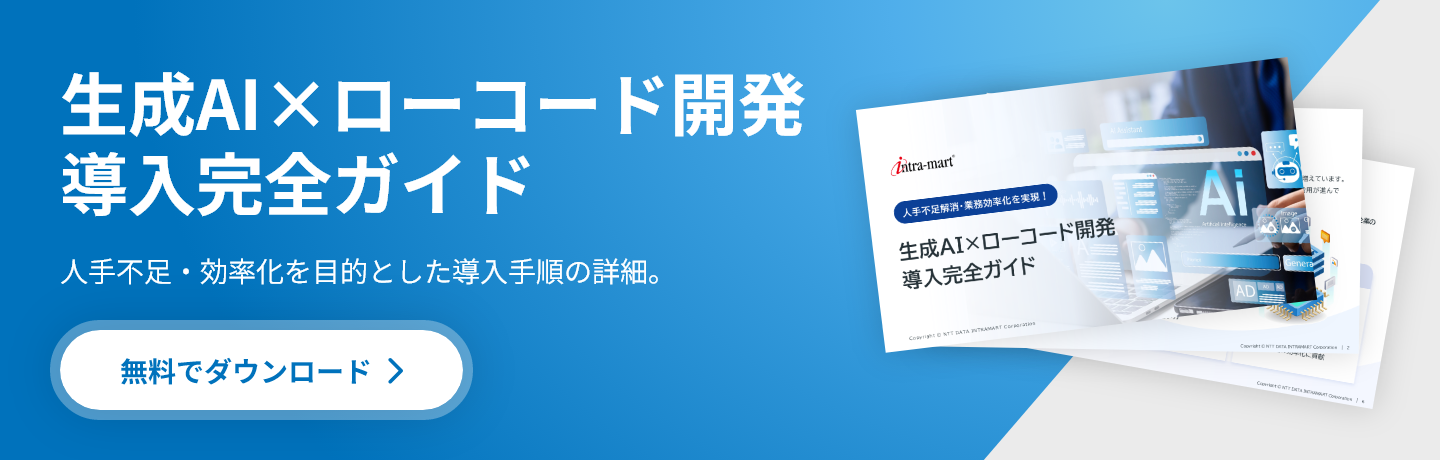
デザインスプリントとは
デザインスプリント(The Design Sprint)とは、米Google社のベンチャーキャピタル部門として設立された、当時のGoogle Ventures社(現在は「GV」に社名変更)が、2015年にスタートアップ企業に向けに提唱した概念で、5日間(40時間)でアイデアからプロトタイプの完成までを完了する、課題解決のためのメソッドです。主に、新たなサービスの創出などに活用されます。
デザイン思考やアジャイル開発、ハッカー・ウェイの要素を取り入れ、ユーザーの声をフィードバックしながら、アイデアの価値を短期間で検証する点が特徴です。
デザインスプリントとデザイン思考の違い
デザインスプリントの要素の一つとなっているのが「デザイン思考」です。
デザイン思考(Design Thinking)とは、デザイナーなどのクリエイターが業務の中でデザインする際の思考プロセスを、未知の課題を解決する際に活用しようというものです。
アイデアを積み上げていくことや、ユーザーの満足・共感に重点を置くことなどが特徴です。
アジャイル開発とは
アジャイル開発とは、開発対象を機能単位に分解し、それぞれの機能開発で「計画→設計→実装→テスト」のサイクルを素早く回しながら開発を進めていく開発手法です。
それまでソフトウェア開発において主流だったウォーターフォール開発の欠点を改善するために生まれたもので、迅速性や柔軟性を重視したもので、開発期間の短縮やユーザビリティの向上といったメリットを持ちます。
アジャイル開発について詳しくは、下記の記事もご覧ください。
【関連記事】
アジャイル開発のメリットやデメリットから進める方法まで徹底解説
ハッカー・ウェイとは
ハッカー・ウェイ(The Hacker Way)とは、2012年5月に米ナスダック市場に株式を上場した際に、当時のFacebook(現:Meta)の創業者の一人であったマーク・ザッカーバーグが投資家に向けて書いた手紙で使用した言葉で、ハッカーの、改善を継続的に繰り返し、一度にすべてを完成させずに長期にわたって最良とされるサービスを作る点、オープンで実力主義重視な文化といった特徴を活用した、同社の企業文化であり経営手法です。
デザインスプリントのメリット
デザインスプリントを活用することで、具体的にどのようなメリットが得られるのでしょうか?
発案からユーザーの反応までを検証できる
デザインスプリントでは、アイデアからプロトタイプの完成までを完了させるメソッドです。
このため、正しくデザインスプリントを実施すれば、5日後には、あるサービスアイデアについてのユーザーの反応までを網羅できることになります。
早い段階で軌道修正が行える
前項でお伝えしたように、デザインスプリントでは、5日間(40時間)という短期間で実施するため、スピーディに改善点を見つけることができます。
早い段階で軌道修正が行えるということは、それだけ競争力の強化にもつながります。
低コストで実施できる
デザインスプリントは、5日間(40時間)という短期間で実施します。
このため、検証にかかる、人件費を中心とするコストを低く抑えることができます。
デザインスプリントの実行プロセス
冒頭でもお伝えしたように、デザインスプリントは5日間(40時間)で完成するようにプログラムが組まれています。
各日に行うべきプロセスは次の通りです。
1日目:理解
1日目で、課題を理解します。
関係者全員を集めて、課題が生じるに至った経緯や、現時点で認識されている課題について、関係者一人ひとりが知る情報を共有します。必要に応じて、ユーザーインタビューやデータ分析なども実施します。
さらに、明確になった課題に対して関係者が活用できそうな知識やスキルについても可視化します。
2日目:スケッチ
1日目で明らかにした課題と周辺情報、関係者のスキルなどを元に、実際にどのような解決策があるか、関係者全員でアイデアを出し合います。
さらに、アイデアごとに実現性を検討するため、チーム分けを行います。
3日目:決定
2日目に作成したチームごとに、解決策の詳細について検討します。
この内容を関係者全員で共有して話し合い、どの解決案を検証するかを決定します。
可能であれば1つに、選び切れない場合も2つ程度までに絞りましょう。
4日目:試作
3日目で決定した解決案について、プロトタイプ(試作品)を作成します。
5日目の検証で実際にユーザーが使用できるよう、UIデザインも行いましょう。
5日目:検証
4日目で作成したプロトタイプを用いて、実際のユーザーを対象にアイデアを試行します。
ユーザーがどのようにプロトタイプと接するか、データを取得するほか、ユーザーの反応などを観察し、さらに、ユーザーから直接のヒアリングも行って、評価を聞き取ります。
取得したデータを分析して、3日目に決定した仮説の検証を行いましょう。
デザインスプリントを実行する際の注意点
デザインスプリントを実施する際は、下記の3点に注意して行うことが重要です。
課題解決よりも仮説の検証に重点を置くこと
デザインスプリントは、課題解決のためのメソッドですが、最初から課題を解決できる正しい方法を得ようとすると、デザインスプリントの“短期間で仮説を検証できる”という強みを十分に活かすことができません。
最初の1サイクル目から正しい結果を得ようとするのではなく、まずは決定した仮説を検証することに注力し、解決できなければ次のサイクルを回すことを考えましょう。
5日間の期間とプロセスをきちんと守る
デザインスプリントの参加者が多忙の場合などでは、たった5日間のスケジュールですら確保しづらいこともあるかもしれません。しかし、「デザインスプリントの実行プロセス」でご紹介した日程とプロセスは省略せずに実施する必要があります。
逆に、成果を求めるあまり、5日間のどこかのプロセスでスケジュールを延長したくなる可能性もあります。この場合も、各日でプロセスを締め切り、次のプロセスに移ることが大切です。
上記の「課題解決よりも仮説の検証に重点を置くこと」とも重複しますが、たとえ「精度が低い」と感じる仮説であったとしても、まずは仮説を検証して結果を得ることを重視してください。
どのような課題にも適応するわけではないことを知る
デザインスプリントは、課題解決のためのメソッドの一つであり、どのようなタイプの課題も解決できる万能薬というわけではありません。特に、新たなサービスを創出したい際などを中心に活用されていることからも、向き・不向きがある方法であることは否めません。
何度かサイクルを回してみても手ごたえが感じられない場合は、別のメソッドを試すなど、ほかのアプローチで課題解決に当たりましょう。
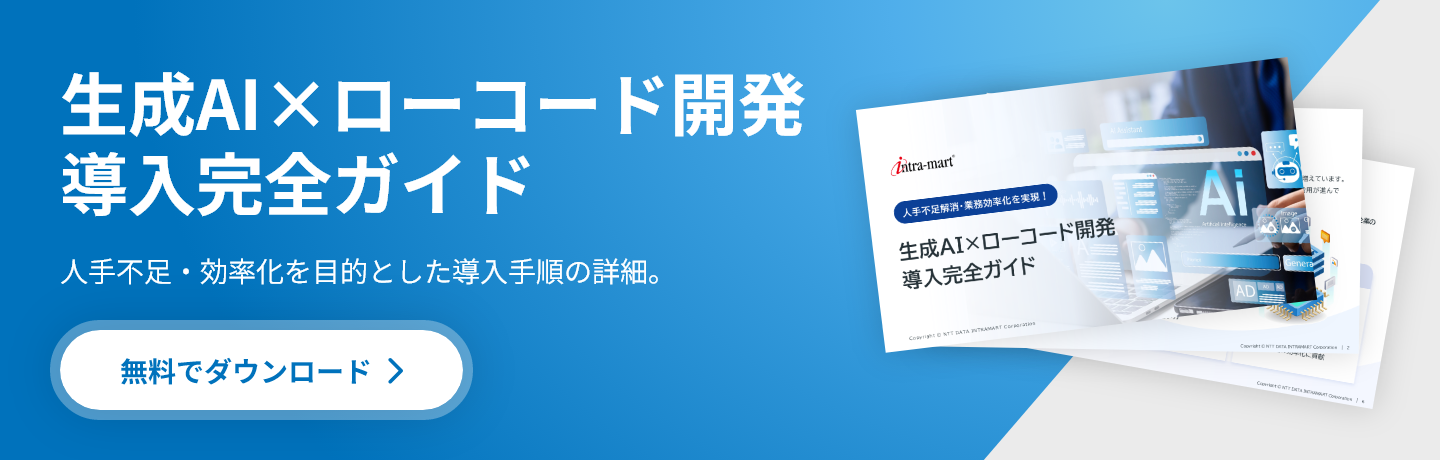
まとめ
デザインスプリントは、デザイン思考やアジャイル開発などの要素を取り込んだ課題解決手法で、5日間という短期間で仮説を検証できる点に大きな特徴があります。
スタートアップ企業に向けに提唱された手法であることからも新サービス創出時に向いており、すべての課題を解決できるわけではありません。
実施する際は、5日間の期間とプロセスを守り、仮説の検証に重点を置いて活用しましょう。
Concept Book
ローコード開発・業務プロセスのデジタル化で豊富な実績を持つintra-martが、お客様のビジネスにどのような効果をもたらすのか、特長や導入効果など製品コンセプトを詳しくご紹介しています。

お困りごとがありましたら、お気軽にご相談頂ければと思います。
















