AIを活用したワークフローとは?活用例や導入メリットを解説

生成AIをはじめとしたAI技術を活用したワークフローを導入する企業が増えてきています。AIワークフローは、従来のワークフローよりも自動化できる業務範囲が広く、業務効率の向上やエラー削減などを図れるのがメリットです。
とはいえ、「AIを取り入れるだけで本当に業務が改善されるのか分からない」「具体的な活用例や効果を知りたい」と感じている方も多いのではないでしょうか。
実際、AIワークフローと一口に言っても、その種類や導入方法はさまざまです。
そこで本記事では、AIワークフローとは何か、メリットや活用事例などを解説します。従来のワークフローとの違いや導入時のポイントも紹介するので、ぜひ最後までチェックしてみてください。
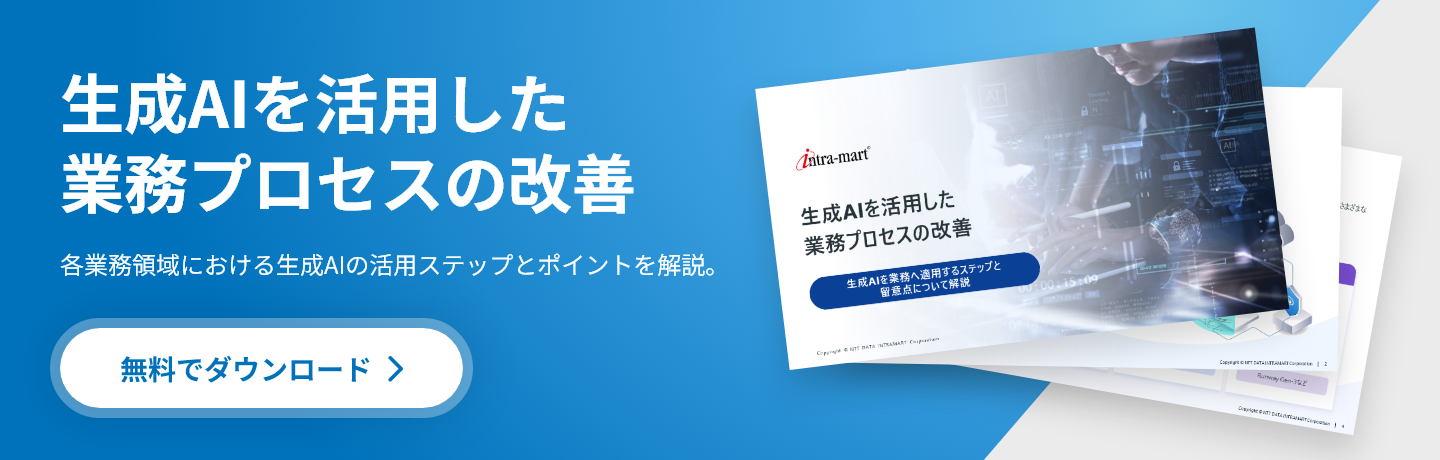
AIを活用したワークフローとは
AIを活用したワークフローとは、企業内の業務手順や処理の流れに生成AIなどのAI技術を組み込み、自動化や最適化を実現する仕組みのことを指します。
従来のワークフロー管理システムは、あらかじめ決められたフローに沿って作業を進めるものでしたが、AIを取り入れることで、以下のような高度な処理が可能になります。
<AIを活用したワークフローにできること>
・曖昧な入力情報でも判断できる
・過去の傾向を学習して業務手順を最適化する
・処理の途中で例外が発生しても柔軟に対応できる
AIワークフローは従来の「ルールベースの自動化(RPA)」をさらに進化させたもので、変化に強く、判断を伴う業務にも対応できる点が特徴です。定型作業だけでなく、複雑な業務でも活用できるため、幅広い業種・部門で注目されています。
AIワークフローの活用例
AIワークフローは、業務の種類を問わず多くの領域で活用が進んでいます。
顧客対応業務(カスタマーサポート)
顧客対応業務は、AIワークフローを活用しやすい業務の1つです。チャットボットや自動応答システムと連携し、問い合わせ内容をAIが分類・理解して適切な部門に振り分けたり、即座にFAQを提示したりすることで、顧客対応のスピードと品質を両立できます。
さらに、AIが過去の対応履歴を分析し、顧客の次の質問を予測するような先読み対応も可能です。
経理・財務業務
AIは、画像から情報を抽出・認識することが可能です。これを経理・財務業務に活用すると、請求書の読み取りや仕訳処理など、紙書類やPDFに含まれる情報をAIが抽出・認識し、会計ソフトへの自動入力や確認フローへの連携が可能になります。
上記のような利点から、AIワークフローは、経理・財務業務におけるミスの防止や作業時間の短縮に効果的です。
人事・採用業務
AIワークフローは、人事・採用業務にも活用できます。
たとえば、応募者の履歴書や職務経歴書をAIが解析し、求めるスキル・経験とのマッチ度を自動評価することが可能です。これにより、書類選考の精度向上と負荷軽減が期待できます。面接日程の調整や通知業務といった定型業務も自動化の対象です。
製造業における不良品検知
製造業における不良品検知では、画像認識AIが利用されています。画像認識AIを使えば、製品ライン上でリアルタイムに不良品を検出し、自動的に除外するワークフローを構築可能です。作業員の目視による検査から脱却し、品質管理の精度と効率を両立できます。
契約書レビュー
契約書の内容をAIが読み取り、リスクのある条文や抜け漏れを指摘するワークフローが実用化されています。法務担当者の確認作業を補助する形でAI技術を活用すれば、契約処理のスピードと安全性を高められるでしょう。
従来のワークフローとの違い
AIワークフローと従来のワークフローの大きな違いは、柔軟性と学習能力にあります。
従来のワークフローは、事前に設定する固定ルールのとおりにしか動かないため、固定ルールの質によって利便性が大きく左右されます。一方、AIワークフローは、過去のデータや状況から判断ができるため、環境の変化や業務の複雑化に強く、将来的な拡張性にも優れているのが特徴です。
ワークフローに改善が必要なときやエラー発生時は、従来のワークフローの場合は固定ルールのどこに問題があるのかを特定し、人の手で修正する必要があります。対してAIワークフローは、学習や予測により自動で改善が可能です。
このように、従来のワークフローでは固定ルールの設定・修正に人の手が介入するため、属人化しやすい点にも注意する必要があります。一方のAIワークフローは、AIが各種判断を自動的に行うため、属人化しにくいのも特徴的です。
AIワークフローの導入メリット
AIワークフローの導入メリットとしては、主に以下の5つが挙げられます。
・業務効率の向上 ・エラーの削減
・属人化の解消 ・顧客満足度の向上
・意思決定のスピード向上
業務効率の向上
AIを活用することで、業務プロセスの一部または全体を自動化でき、作業時間の短縮・人手不足の解消につながります。たとえば、1件あたり10分かかっていた作業が1分で終わるようになれば、月間で数十時間の工数削減が見込めるでしょう。
また、AIは24時間365日稼働できるため、夜間・休日の処理も可能です。これにより、業務の遅延リスクが軽減され、対応スピードが格段に向上します。特に、膨大なデータ処理や大量の問い合わせ対応など、人手では対応しきれない領域では効果を発揮するでしょう。
業務の効率化は、単に時間を短縮するだけでなく、社員が本来やるべき業務に集中できる環境を整えることでもあります。人の手で行う必要のない業務をAIに任せることで、生産性向上や働き方改革の実現も期待できます。
エラーの削減
人の手による業務には、どうしてもヒューマンエラーがつきものです。その点、AIは人間と異なり、疲れたり注意力が散漫になったりすることがありません。AIワークフローを活用すれば、単純作業や反復作業において、ミスの発生を大幅に減らすことができます。
たとえば、請求金額の入力ミス・顧客情報の記入漏れ・承認フローの通し忘れといったケアレスミスは、手動処理では避けにくいものです。AIワークフローでは、入力情報を自動で検証・補完する機能があり、不備のある処理を早い段階で検知・修正できます。
また、過去のエラー履歴を学習し、同様の事態が発生する前に警告を出すといった予防的なアプローチも可能です。結果として、業務品質が向上し、顧客や取引先からの信頼にもつながるでしょう。
属人化の解消
属人化とは、特定の人にしかできない業務が存在してしまうことです。担当者が不在の際に仕事が止まる、ミスが起きやすくなるといった課題があります。AIワークフローの導入により、このような属人化を大きく解消できます。
AIは判断の基準を明文化し、それをもとに一貫した処理を行うため、特定の担当者の経験や勘に依存しなくても業務を回すことが可能です。さらに、処理内容や結果がシステム上にログとして記録されるため、「誰が、いつ、何を判断したのか」を可視化できます。これにより、引き継ぎや監査にも対応しやすくなるでしょう。
また、新人教育にもAIの判断ロジックを活用できるため、知見の蓄積・継承にも役立ちます。属人化の排除は、組織の持続的成長を支える重要な要素です。
顧客満足度の向上
AIワークフローの導入は、顧客満足度の向上にも繋がります。たとえば、AIチャットボットとワークフローを連携させることで、問い合わせ対応を自動化しつつ、顧客の要望に即座に応答できる体制が整います。
従来のように、問い合わせから回答までに数日を要する顧客対応をAIが効率化すれば、顧客は迅速かつ的確なサポートを受けられるようになります。また、過去の問い合わせ履歴や行動パターンをAIが分析することで、顧客に合わせた個別対応も実現可能です。
意思決定のスピード向上
AIワークフローの導入により、意思決定に必要な情報の収集・分析・整理のスピードが飛躍的に高まります。これまで担当者が複数の資料やデータを手作業でまとめていた工程を、AIが自動で可視化・要約することで、迅速な判断が可能です。
たとえば、営業日報や市場データをもとに、次に提案すべき商材や施策をAIがレコメンドする仕組みを組み込めば、現場の対応スピードが向上し、機会損失の防止にもつながります。経営層向けにも、KPIの異常やリスク兆候をリアルタイムで通知するAIワークフローを活用することで、経営判断の迅速化が期待できるでしょう。
AIワークフロー導入時のポイント
AIワークフローを導入する際には、以下のようなポイントをおさえることが大切です。
目的と対象業務を明確にする
最初に取り組むべきは、AIワークフローの導入目的と活用する業務を明確にすることです。導入目的が曖昧なまま進めてしまうと、成果が実感できず、現場に受け入れられない可能性があるため注意しましょう。
たとえば、「問い合わせ対応のスピードを改善したい」「ミスの多い承認業務を自動化したい」など、解決したい課題や期待する効果を具体的に整理することが重要です。
AIの学習に使うデータを整備する
AIはデータから学習して判断を行うため、質の高いデータが不可欠です。業務フローで扱うデータが散在していたり、形式がバラバラだったりすると、AIが正しく動作しない可能性があります。そのため、導入前にデータの収集元・保存形式・更新頻度などを確認し、整備することが必要です。
また、AIワークフローは他の業務システムと連携するケースが多いため、既存の業務ツールとの統合性も事前に確認しましょう。APIの有無や、RPAなどとの併用可否も含めて検討することで、スムーズな導入が実現できます。
段階的にAIワークフローを導入する
一度に全社へAIワークフローを導入しようとすると、現場が混乱するリスクがあります。AIワークフローの導入時は、まずは一部の部署・業務に絞って試験運用からはじめるスモールスタートがおすすめです。
経費精算や顧客データ入力など、一部の業務にのみAIワークフローを導入することで、初期投資とリスクを低減できます。また、導入効果を検証しやすいため、改善したり、ほかの業務への展開を図ったりと、次のアクションを取りやすくなります。
成果の可視化と継続的な改善
AIは導入して終わりではなく、継続的な改善が必要です。定期的に結果を振り返り、AIの判断精度を調整したり、新たな業務へ拡張したりすることで、導入効果を最大化していくことができます。
AIワークフローの導入効果を評価するためには、定量的な指標で成果を可視化することが重要です。たとえば、業務処理時間の短縮率・エラー件数の削減数・対応完了までの平均日数など、導入前後のパフォーマンス差を数値で確認しましょう。
まとめ
本記事では、AIワークフローとは何か、活用例や従来のワークフローとの違いなどを解説しました。AIワークフローは、固定ルールに従う従来のワークフローと異なり、過去のデータなどから学習してさまざまな業務に対応できるのが特徴です。
AIワークフローは、単なる自動化を超えて、企業の業務変革に直結する可能性を持つ仕組みです。
業務に課題を感じている方は、まずはスモールスタートで一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。
Concept Book
ローコード開発・業務プロセスのデジタル化で豊富な実績を持つintra-martが、お客様のビジネスにどのような効果をもたらすのか、特長や導入効果など製品コンセプトを詳しくご紹介しています。

お困りごとがありましたら、お気軽にご相談頂ければと思います。

















